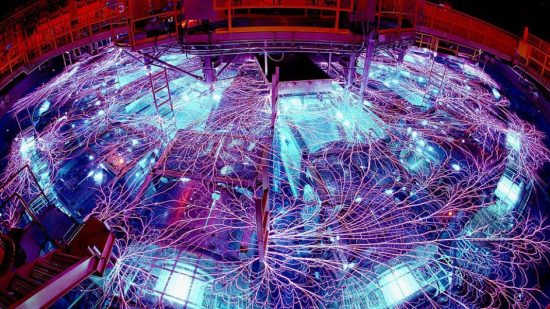「スポーツと医科学は接近しつつあります。これから、医科学チームがスポーツをコンサルティングするニーズはますます高くなっていき、そういったビジネスが生まれてくるのでは、と見ています」。
こう話すのは、牧田総合病院脳神経外科の朝本俊司医師である。昨年、大学での教授職を辞し、民間病院で医療現場に携わりながらアスリートの「呼気分析」の研究に取り組んでいる朝本医師は、MITテクノロジーレビューが6月6日に開催したカンファレンス「スポーツ医科学と人々の健康の未来」に登壇し、スポーツ分野における医科学の課題と機会を語った。
朝本医師がスポーツ医科学における先進事例として挙げたのが、平昌オリンピックでのイ・ヨンヒ医師が率いたメディカル・チームである。イ医師は約400名の医師を含む約3400名のメディカル・チームを立ち上げ、オリンピック選手らを支援。特に、世界に先駆けて精神科医と心理カウンセラーを起用し、「心までケアするメディカル・チーム」としたことが高い評価を受けている。
だが、イ医師が高い志をもってかつて視察に訪れたという長野オリンピック(1998年)では、「ACLS(救急救命における心肺蘇生法)」という言葉すら日本オリンピック委員会の間では知られていなかったという。朝本医師によれば、日本の医療現場では人的資源は優れていても、設備導入や組織体制は「10年遅れている」。その背景として閉鎖的な島国文化、長い歴史が持つ独特の死生観や倫理観の影響があるのではないか、と指摘する。

スポーツ庁の理念と「Sports for all」精神の乖離
2010年には「国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む」ことを目的とした「スポーツ庁」が誕生した。当初の年間予算は12億円だったが、2017年度には402億にまで増額。だが、その中身は、子どもがスポーツに触れるための学校や地域のための予算が51億円、エリートアスリートを育てるための予算が177億円である。
一方、フランスではスポーツ関連予算の約83%が子どもや一般人のためのいわゆる「草の根スポーツ」に配分されており、メダル輩出国と言われるオランダでも関連予算の約7割が国民のスポーツ推進のために使われている。欧州では富裕層の特権となっていたスポーツを民主化する「Sports for all」という考え方が広がり、「すべての人々が身近で手軽にスポーツを楽しむことのできる環境を整備すること」に取り組む動きが盛んだという。その結果、多様な子どもたちがスポーツに触れる機会が生まれ、優れたスポーツ人材が見出された要因の1つとなっている。
「日本にとって、いまだにメダル争いは『軍拡競争』のようなもの」。日本のスポーツ界にもパラダイムシフトが必要だという。
呼気分析の可能性に着目
朝本医師自身が取り組んでいる研究が、「呼気分析による脳震盪の見える化」である。スポーツにおける脳震盪のリスクは、2015年に公開された映画「コンカッション」によってクローズアップされた。著名なアメリカンフットボール選手であるマイク・ウェブスターの変死を取り調べた医師が、死因は脳震盪にあると判断、学会報告したという実話に基づく映画である。映画をきっかけにNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)では集団訴訟が起こり、総額1200億円もの賠償金が支払われることになった。
「残念ながら、現代の医学では脳震盪の診断は選手自身の自覚症状に委ねるしかありません」。朝本医師はこう説明する。脳震盪を起こした選手を復帰させるタイミングを客観判断できないことは、コーチにも選手にも不利益をもたらしているという。
「MRI、血液検査などで評価できるとした報告はいくつかありますが、どれも、手間がかかりすぎたり、検査費用が高額になってしまったりで、現実的ではありません」。
そこで朝本医師が着目したのが「呼気分析」である。検体は特殊なバッグに息を吹き込むだけ。スポーツをする前後で息の成分をイオンレベルまで細分化して分析すると、いくつかの物質の変化により脳震盪を客観的に判断できるというものだ。朝本医師は所属するアイスホッケーチームのほか、脳震盪の多いスポーツであるボクシング選手の協力を得て、立証に向けてのデータ蓄積を進めている。
さらに、呼気分析の用途は脳震盪の診断だけではない。昨今の国際大会においてますます問題になっているドーピング検査や、スポーツ以外の分野でも応用できる可能性があるという。
「病気の治療で薬を投与する患者さんに協力をお願いして、投与前後の呼気分析を実施しました。その結果、驚くべきデータが現れつつあります」。
現在のドーピング検査は血液と尿である。これを呼気で実施できれば、体に針をさすこともなく公開状態でサンプルを採取できる。データ保存することで現状義務化されているサンプルの10年保存、という条件もクリアできるそうだ。
「呼気分析は脳震盪やドーピングに限らず、子どもたちの成長に伴う問題や加齢による認知症の評価などにも応用していけるのではないか、と期待しています」。
スポーツと産業を結びつけて持続可能な社会を作る
講演後は朝本医師が理事を務めている一般財団法人グリーンスポーツアライアンスの澤田陽樹氏を交え、参加者らの質問に応えながら、スポーツと医科学のこれからの可能性を探るディスカッションが実施された。

グリーンスポーツアライアンスは、2008年に米国にてポール・アレンによって創設された同名NPOの日本法人である。米国内では「スポーツとサスティナビリティ」をテーマに、プロや大学のチーム、関連施設や企業らが参加している。日本では2017年末から活動を開始し、スポーツを「プラットフォーム」として捉えることで持続可能なものにしていくことを目指している。
日本のスポーツ医科学と健康を取り巻く状況は、これからどうなるのだろうか?
「スポーツ庁と厚生労働省がスポーツと健康増進を関連付けた施策強化するために連絡会議を設置したという報道がありました。スポーツを健康の保持、増進にもっていくことで医療費や薬剤費が削減でき、企業の医療保険費も、健康組合の負担も軽減できます。いみじくもこれは、私たちの考えとも一致します」(澤田代表)
EUでは、人口の半数近くが運動をしていないという調査結果が出ている。体を動かさないことは成人病リスクを押し上げ、国の医療福祉予算を圧迫する。そのため、EU各国はかなりの危機感をもって施策に取り組んでいるという。
「日本では、学校教育の中で週に2回は『体育』の授業があります。他の国ではほとんど聞いたことがありません。米国でも欧州でもスポーツは自主的なアクションに委ねられている。日本では、子どものうちにスポーツに触れる機会があるわけですから、大きなポテンシャルがあると思っています」(澤田代表)。
では、スポーツの世界にイノベーションを起こすのには、何が必要なのだろう?
「仲間です。もっと日本のアスリートたちのために、また国民の健康のためにボランタリー精神を持って協力してくれる仲間を増やしたい。仲間が増えてくれれば研究はもっとスピードアップできます」(朝本医師)
実際に朝本医師の呼気分析の研究は、グリーンスポーツアライアンスとアスリートや機器メーカーとの協業によって進められている。グリーンスポーツアライアンスはこうしたネットワーキングの機会創出に取り組んでいるという。
「『スポーツは感動を生む』という言葉があります。スポーツは心を豊かにしてくれます。すべての国民がスポーツに触れて感動し、健全になっていく、そういうことをサポートしたいと思っています」(朝本医師)。
- 人気の記事ランキング
-
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製
- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏
| タグ |
|---|
- 清水眞理 [Mari Shimizu]日本版 ゲスト著者
- 一般財団法人グリーンスポーツアライアンス グリーンクリエイティブディレクター。イベント・広告の企画制作会社にて立案された企画を具現化するためのあらゆるクリエイティブワークに携わる。2012年フリーランスとなり、2018年より同財団の運営に参画している。