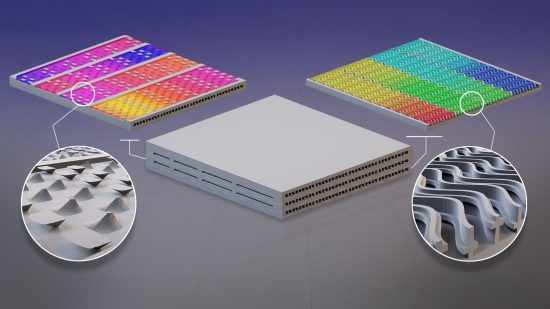地球温暖化は現実
猛吹雪も洪水も人間が原因だ
異常気象を地球温暖化に結びつけると、地球上の災害をスローモーションのように理解しやすくなる。 by Michael Reilly2016.09.09
突然の猛吹雪が米国東海岸を襲っても、米国中西部で豪雨による洪水が起きても、つい最近までは「気候変動が理由で」とはなかなかいえなかった。地球温暖化は実際に起きている、とされていたが、気候学は地球全体のスケールで起きる変化を理解する学問であり、個々の気象現象を予測できるわけではない、と考えるのが科学的態度というものだった。
しかし、ルイジアナ州を襲った豪雨(760mmの激しい雨がルイジアナ州南部に降り注ぎ、洪水で13人が死亡、数万人が避難を強いられた)からわずか数週間後、その考え方は大きく変化している。米国海洋大気庁の研究者は、この豪雨の気象データを取得し、高解像度の気象モデルに当てはめ、既に分析結果を得ているのだ。
研究グループの報告によれば、ガルフコースト(ルイジアナ州など、おもにメキシコ湾の沿岸州のこと)で壊滅的な規模の大雨が降る確率は、かつては50年に一度だった。だが、気候変動によって、30年に一度にまで、確率が40%も高くなったのだ(研究チームの話では、これでも控えめな見積もり)。別の言い方をすると、次の大洪水の発生までに、この地域の住民が復旧・復興に使える時間は、以前よりずっと短くなっているのだ。

こうした観点の研究は、比較的新しい。科学者は、温室効果ガスが長期的な気候に与える影響(ハリケーン、干ばつ、モンスーンなどが季節ごとに起きる頻度など)については、以前からモデル化してきた。しかし、研究者が短期的な気象データを取得し、モデルを使って膨大な数のシミュレーションを実行し、有意性を確認できるレベルで、さまざまな気象現象が、人間の活動によって異常気象を引き起こす方向に作用したかを計算し、結果を得るのは、非常に困難な課題だった。コンピューターによる演算能力と、地球環境の分析に使えるモデルが、このレベルにまで進歩したのは、つい最近のことだ。
各保険会社も、異常な気象現象が起きた際にどの家が冠水してしまうのか、数mの精度で予測できる手法を発見している。保険会社の手法は、気象モデルを使う研究者とは異なるが、保険加入者に注意を促し、住居への被害を抑える対策をとってもらうのに役立つ例もある。
この種の研究には、希望もある。地球温暖化が単なる抽象的概念でなくなることだ。地球温暖化の影響は、普通の人には理解しがたいと思われてきたが、そうではない。科学は、100年間で海面がどれだけ上昇する可能性があるか、恐ろしい数値を並べるやり方をとる代わりに、今、被害をこうむっている天災のうち、どれだけが人類の責任なのか(時に心痛む事実を示しながら)詳細にわたって説明できる段階に到達しているのだ。
(関連記事:Climate Central, Washington Post, New Scientist, “Climate Change Is Challenging the Time-Tested Assumptions Behind Insurance”)
- 人気の記事ランキング
-
- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態
- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由
- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態
- How to have a child in the digital age 「あなたはもうママですね」 ネット・デジタルが約束する 「完璧な出産」の幻想
- マイケル レイリー [Michael Reilly]米国版 ニュース・解説担当級上級編集者
- マイケル・レイリーはニュースと解説担当の上級編集者です。ニュースに何かがあれば、おそらくそのニュースについて何か言いたいことがあります。また、MIT Technology Review(米国版)のメイン・ニュースレターであるザ・ダウンロードを作りました(ぜひ購読してください)。 MIT Technology Reviewに参加する以前は、ニューサイエンティスト誌のボストン支局長でした。科学やテクノロジーのあらゆる話題について書いてきましたので、得意分野を聞かれると困ります(元地質学者なので、火山の話は大好きです)。