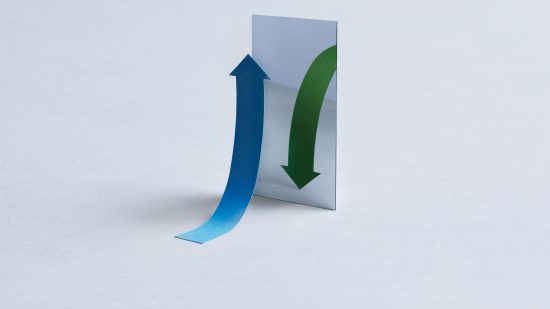脳コンピューター・インターフェイスの実用化には何が必要か
脳コンピューター・インターフェイス研究の先駆者は、実用化には程遠いと語った。装置の小型化、ニューラルコードの解明がまだまだ必要だという。 by Emily Mullin2017.11.13
脳コンピューター・インターフェイスは、身体がまひした人や腕をなくした人が、髪をとかしたりテレビのリモコンを操作したりといった日常作業を、思い浮かべるだけで実際にできるようにするための手段として、数十年前から構想されてきた。
そういったロボット装置は、すでにある。しかし、今のところ、少数の患者が世界各地の研究所で装置をテストし、限られた範囲の動作に成功しているにすぎない。しかし、ピッツバーグ大学の著名な神経生物学者、アンドリュー・シュワルツ教授によると、研究者たちは依然として、そうした装置の一般家庭での実用化はほど遠いと考えているという。
11月7日、MITテクノロジーレビュー主催の年次カンファレンス「EmTech」に登壇したシュワルツ教授は、脳コンピューター・インターフェイス実用化のためには数多くの改良が必要だと述べた。ケンブリッジに拠点を置くチャールズ・スターク・ドレイパー研究所と協力して改良モデルの開発に取り組んでいるが、プロジェクトを進めるための資金が不足しているという。
「このプロジェクトは科学の中でもかなり辺縁部に位置する研究なのです」と、脳コンピューター・インターフェイスの先駆者であるシュワルツ教授は述べた。
現在の脳コンピューター・インターフェイスは、脳内または頭に電極あるいはチップを取り付け、外部のコンピューターとやりとりをする。電極が脳波を収集し、コンピューターに送信すると、脳波は特殊なソフトウェアによって解析され、動作命令に変換される。命令はロボット・アームなどの機械に伝達され、患者が望んだ動作が実行される。
豆粒ほどの大きさの埋め込みチップは、頭頂部に固定したペデスタルと呼ばれる基部に取り付けられ、ケーブルを介してコンピューターに接続される。ロボット・アームもコンピューターにつながっている。つまり、この不格好な仕組みが、患者が自宅でこのインターフェイスを利用するのが不可能だということを意味しているのだ。
家庭での実用化にたどり着くためには、コンピューターを携帯できるほど小型化し、車椅子に設置できるロボット・アームを作り、インターフェイス全体を無線化し、患者の頭部に取り付ける重たいペデスタルをなくす必要があると、シュワルツ教授は言う。
ゆくゆくは、まひ患者がこの種のインターフェイスを使用して、ロボット・アームだけではなく、あらゆる種類の機器を操作できるようになればいいと考えている、とシュワルツ教授は述べた。
「遠隔操作が使える人がスマート・ホームに足を踏み入れ、思考するだけであらゆる機器を使いこなせる、そんな場面を想像してみてください」。
大きな障害となっているのは、この技術の背景が非常に複雑なことだ。インターフェイスは「ニューラル・コード」、つまり脳のニューロンの活動パターンが動作命令に変換され伝達されることで動く。しかし、動作によってさまざまに異なるニューロンの発火パターンについて分かっていることは、ほんのわずかしかない。そのため、このインターフェイスを使って実行できる動作の種類は今のところ限られている。
たとえば、シュワルツ教授と研究チームは被検体として人間の他にもサルを加えて実験をして、脳コンピューター・インターフェイスとロボット・アームを使って物をつかむことに成功した。しかし、物を押したり引いたりといった物体に力を加える動作はより複雑で、コンピューターのアルゴリズムに種類の異なる一連のニューラル・コード・セットを学習させる必要がある。
「人が物体を扱うのに、動作と力の関係をどのように効果的に調整すればよいのかということついては、まだよく分かっていないのです」とシュワルツ教授は述べた。そのようなニューラル・コードがどのようなものかを理解するために、科学者は脳についてもっとよく研究しなければならないだろう。
- 人気の記事ランキング
-
- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法
- The paints, coatings, and chemicals making the world a cooler place 数千年前の知恵、現代に エネルギー要らずの温暖化対策
- This Nobel Prize–winning chemist dreams of making water from thin air 空気から水を作る技術—— ノーベル賞化学者の夢、 幼少期の水汲み体験が原点
- Quantum navigation could solve the military’s GPS jamming problem ロシアGPS妨害で注目の「量子航法」技術、その実力と課題は?
- エミリー マリン [Emily Mullin]米国版
- ピッツバーグを拠点にバイオテクノロジー関連を取材するフリーランス・ジャーナリスト。2018年までMITテクノロジーレビューの医学生物学担当編集者を務めた。