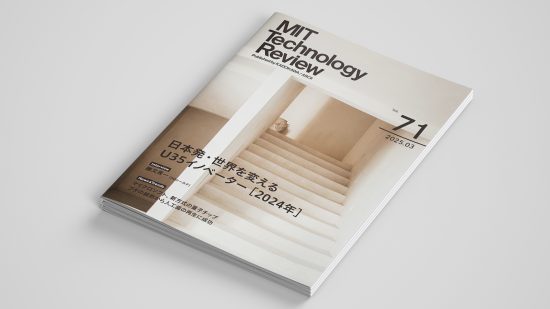「終末の氷河」救えるか?
海面上昇を食い止める
新プロジェクトが始動
「終末の氷河」の異名をとる南極のスウェイツ氷河が地球温暖化で海に流れ出せば、海面が上昇し、気球規模の気候災害が起こる可能性がある。海面上昇予測の改善と氷河の再凍結の可能性を探るために新たな取り組みが始まっている。 by James Temple2025.03.25
- この記事の3つのポイント
-
- スウェイツ氷河の崩壊が海面上昇をもたらす可能性がある
- アレート氷河イニシアチブは氷河研究に資金提供し理解を深める取り組み
- 氷河を再凍結させる介入は技術的課題があるが研究の価値はある
南極のスウェイツ氷河は、フロリダよりも大きな氷の要塞だ。西南極の岩盤上にある約1200メートルの高さの氷の壁で、背後にある低地の氷床を守っている。
しかし、強く暖かい海流により氷河の土台が弱まり、アムンゼン海へと滑り込む速さが加速している。科学者たちは、この海水が今後、数十年のうちに氷の壁を崩壊させ、西南極氷床に亀裂を生じさせる暴走プロセスを始動させてしまうのではないかと懸念している。
そうなれば、地球規模の気候災害が始まることになる。スウェイツ氷河自体が海面を60センチメートル以上上昇させるのに十分な氷を保持しているため、海岸線が浸水し、低地に住む何千万人もの人々が自分たちの家を放棄せざるを得なくなる可能性がある。
まだ何世紀もかかる可能性があるが、氷床全体が失われたら海面が約3.3メートル上昇し、大陸の輪郭が描き替えられてしまうだろう。
これがスウェイツ氷河が「終末の氷河」と呼ばれる所以だ。そのために科学者たちは、こうした氷河の崩壊がどれほどの確率で起こり得るのか、いつ起こり得るのか、そしてそれを食い止める力が私たちにあるのかを知ろうと、躍起になっている。
マサチューセッツ工科大学(MIT)とダートマス大学の科学者は2024年、これらの疑問に対するより明確な答えを出すことを目指し、「アレート氷河イニシアチブ(Arête Glacier Initiative)」を設立した。この非営利研究組織は、国連による初の「世界氷河デー」に合わせて2025年3月21日に正式に発表され、Webサイトを公開し、研究提案の募集を開始する。MITテクノロジーレビューの独自報道だ。
同イニシアチブはまた、ウィスコンシン大学マディソン校の2人の氷河研究者に、2年間でそれぞれ約20万ドルとなる最初の助成金を提供することも発表する。
アレート氷河イニシアチブの主な目標のひとつは、巨大氷河、具体的にはスウェイツ氷河を岩盤まで再凍結させることでその消失を防ぐ可能性を研究することだ。これは自然界に対する抜本的な介入であり、人里離れた危険な環境下での大規模で高額な工学プロジェクトが必要となる。
しかし、このような巨大適応プロジェクトは、気候変動難民の大量移住を最小限に抑えることで、大量移住に確実に伴う苦しみや暴力の多くを防ぎ、世界中の高層ビル、道路、住宅、港湾、空港に投資された数兆ドルを各国が守るのに役立つことが期待されている。
「海面上昇1センチメートルにつき約100万人が移住することになります」。MITの地球物理学准教授で、アレート氷河イニシアチブを共同設立し、主任科学者を務めるブレント・ミンチューは語る。「私たちがそれを数センチメートルでも下げることができれば、数百万人の家を守ることができるでしょう」。
しかし、科学者の中には、このアイデアは非現実的で途方もなく費用のかかる目くらましであり、資金、専門知識、時間、資源をより本質的な極地研究活動から引き離してしまうと考える者もいる。
「私たちは工学でできることについて少し楽観的になりすぎることがあります」。コロラド大学ボルダー校にある国立雪氷データセンター(National Snow and Ice Data Center)の副主任科学者、トゥイラ・ムーン博士はこう話す。
「可能性のある2つの未来」
カリフォルニア工科大学で地球物理学の博士号を取得したミンチュー准教授が氷河の研究に惹かれたのは、氷河が世界の温暖化に伴って急速に変貌し、海面上昇の危険性を高めているからだという。
「しかし、何年か経つうちに、事態がどのように進んでいるかを単により劇的に伝えるだけでは満足できなくなり、それに対して私たちには何ができるのかにより関心を向けるようになりました」。この夏からカリフォルニア工科大学に教授として戻る予定のミンチュー准教授は話す。
ミンチュー准教授は2024年3月、ダートマス大学の工学助教授であるコリン・マイヤーと共同でアレート氷河イニシアチブを設立した。2つの大きな疑問に対する科学的理解を深める研究に資金を提供し、監督することを目指している。2つの疑問とは、海面上昇は今後数十年の間にどれほどのリスクをもたらすのか、そしてそのリスクを最小限に抑えることはできるのかだ。
「この2つの課題の両方に対処するためには慈善的な資金援助が必要です。なぜなら、この種の研究には民間からの資金援助がなく、政府からの資金援助もごくわずかだからです」。こう話すのは、メタの元最高技術責任者(CTO)であり、気候変動慈善家に転身したマイク・シュローファーである。シュローファーは、アウトライアー・プロジェクト(Outlier Projects)という自身の新組織を通じてアレート氷河イニシアチブに資金を提供した。
NPOであるアレート氷河イニシアチブは現在、アウトライアーのほか、ナビゲーション・ファンド(Navigation Fund)、キシック・ファミリー財団(Kissick Family Foundation)、スカイ財団(Sky Foundation)、ウェドナー・ファミリー財団(Wedner Family Foundation)、グランサム財団(Grantham Foundation)などからの寄付で約500万ドルの資金を得ている。
ミンチュー准教授によれば、アレートとは氷河が山の両側を削ることで2つの谷の間にできる鋭い山の尾根のことであり、アレート氷河イニシアチブは主にそれにちなんで名付けられた。アレートは氷河の動きを導くものであり、氷河によって形作られるものでもある。
このアレートという組織名は「可能性のある2つの未来」を象徴しているのだとミンチュー准教授は語る。「私たちが何か行動を起こす未来と、何もしない未来です」。
より精度の高い予測
いささか心強いニュースとしては、地球の気温は上昇しているとはいえ、西南極氷床が完全に融解するにはまだ数千年かかる可能性があるということだ。
さらに、今世紀の海面上昇予測は、一般的に0.28メートルから1.10メートルの幅があると、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の最新の報告書に記されている。後者の数値は、温室効果ガス排出量が非常に多いシナリオ(SSP5-8.5)でのみ発生し、世界が現在辿っている軌道を大幅に超えるものだ。
しかし、2100年までに海面が2メートル近く上昇する「低い可能性」も依然と …
- 人気の記事ランキング
-
- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由
- OpenAI has released its first research into how using ChatGPT affects people’s emotional wellbeing チャットGPTとの対話で孤独は深まる? オープンAIとMITが研究
- An ancient man’s remains were hacked apart and kept in a garage 切り刻まれた古代人、破壊的発掘から保存重視へと変わる考古学
- How to have a child in the digital age 「あなたはもうママですね」 ネット・デジタルが約束する 「完璧な出産」の幻想