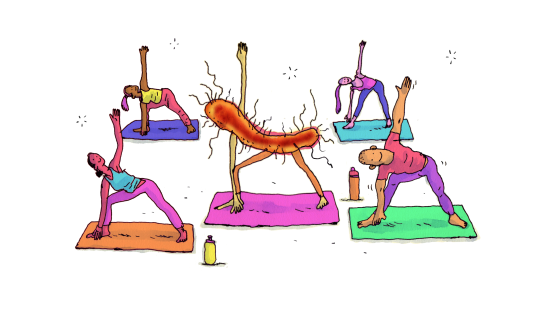苅部太郎:生成AIを用いた表現を通じた「人間」の探求
テクノロジーと人間との関係に関心を持ちながら、人間の認知と人工知能(AI)の関係性を探求する作品を制作してきたアーティスト/写真家の苅部太郎氏にインタビューした。 by Motoki Kobashigawa2025.03.24
この記事は、『AI白書2025 生成AIディション』(角川アスキー総合研究所刊)の転載です。
2025年3月に発売された『AI白書2025 生成AIエディション』の表紙には、アーティスト/写真家である苅部太郎氏の作品『あの海に見える岩を、弓で射よ』(2023年)が使用されている。苅部氏は、報道写真家としてキャリアをスタートし、以来テクノロジーと人間との関係に関心を持ちながら、人間の認知と人工知能(AI)の関係性を探求する作品を制作してきた。作品の制作の狙いと、テクノロジーと表現の関係性について話を聞いた。

膨大な試行錯誤で突如生まれたAIならではの抽象的な表現
――今回の表紙にも使われた一連の作品「あの海に見える岩を、弓で射よ」について、コンセプトを教えてください。
2022年から始まったシリーズで、写真メディアの美術作品という文脈で制作しています。機械や人工知能(AI)の目に幻を見せて風景画を描かせるというコンセプトの作品です。具体的には、アドビのAIモデルである「アドビセンセイ(AdobeSensei)」を使い、本来は風景写真の認識・編集のための機能にノイズだらけの抽象的なデータを入力して、強引に解釈させることで風景の意味を穴埋めさせるという手法を取っています。
この過程で、本来であれば出てこないはずの機械学習された風景の断片が張り出されていきます。AIが無理やり意味を見出そうとする過程で生まれる特異な表現なのです。
――入力する抽象的なデータはどのように作られているのですか。

アーティスト/写真家。写真メディアや、人・マシンの認識システムの根源に立ち戻りながら、「人がものを見る経験」を通して社会の実相を再認識する作風が特徴。一貫して社会的なイシューに関心を持ち、初期は被災地や難民キャンプなどでのフォトジャーナリズム、人形やロボットなどの人工物と関係を結ぶ人々を捉えるドキュメンタリー領域で活動した。近年は先端テクノロジーに主眼をおき、日常的に誰でも使えるソフトウェアを取り入れ、時に意図的に誤った使い方をしながらその性質を暴露する。主な個展に「あの海に見える岩に、弓を射よ」MASQ(東京、2024)、「Electric Caveman」HECTARE(東京、2023)、「沙織」京都国際写真祭 KG+ SELECT(京都、2021)、「Age ofPhoton / INCIDENTS」IMA gallery(東京、2020)、「Saori」PaddingtonTown Hall, Head on Photo Festival(シドニー、2018)など。主な受賞・選出にMAST財団助成金ノミネート(伊、2024)、Japan Photo Award・ElisaMedde賞(2024)、Tokyo Frontline Photo Award /川島崇志賞(東京、2022)、第18回写真「1_WALL」ファイナリスト(東京、2018)など。
テレビ画面に映るニュースやドラマのワンシーンを、意図的に接触不良を起こしてノイズだらけにしたものを使用しています。その画面をカメラで撮影し、回転やトリミングを加えることで、元の文脈を消し去ります。人間が見ても何の映像だったのか分からない状態にするのです。
この手法自体はもともと『INCIDENTS』(2018〜2022年)というシリーズで使っていたものです。人間の鑑賞者は、ノイズ混じりの抽象的なイメージに、オリジナルの視覚情報とは別の何か意味を見出そうとする。この「見立て」のプロセスをシミュレーションしようとしたのが、今回の作品です。
――こうした制作手法を選んだ背景には、どのような考えがあるのでしょうか。
私は大学で心理学を専攻していたこともあり、人間の認知に強い関心があります。人が何かを誤読してしまったり、自分の知っているものに引き寄せて解釈してしまったりする現象に興味があって、錯覚なども研究していました。そこで、AIという新しいレイヤーを加えることで、人間の脳の振る舞いをシミュレーションしようとしました。
2022年から、このノイズの画像をもとにAIに生成させるという作業を繰り返しています。生成した画像は数百枚に及びます。作業を始めた当初は、人間と同じように認識するだろうという仮説通りの結果が得られました。ノイズの中にある輪郭から街並みを見出したり、ギザギザした形状を岩や自然物として解釈したり。ただ、2023年ごろから、出力される画像が徐々に抽象的になっていきました。当初は記号的な置き換えという印象だったのが、次第にAI独自の解釈が加わった、より抽象度の高い表現に感じられるようになったのです。おそらくモデルがアップデートされた影響だと思います。


右:元になった『INCIDENTS』(2018〜2022)の作品。テレビ画面を意図的にノイズまじりにして撮影、加工することで、元の文脈を取り除いている。
――機械であるAIに「解釈が生まれている」というのが興味深いですね。
AIや機械は一般的に中立的な存在として認識されがちですが、そうではありません。実際にはある種の価値観やキャラクターを持っています。悪く言えば、誰かの「バイアス」がかかっているといえます。AIを使用する人はこのことを認識しておく必要があると思います。
2024年11月に発表した新作『TypicalWorld』シリーズは、画像生成AIモデル「ステーブル・ディフュージョン(Stable Diffusion)」の持つバイアスを可視化する試みです。プロンプトの先頭に”typical”(典型的な)という言葉を入れ、その後にさまざまな単語を続けることで、AIが「典型的」と見なすイメージを探っていきました。
例えば「目の色」というプロンプトを入れるとほぼ必ず青い目が生成されたり、「大統領」と入力するとドナルド・トランプ氏のような人物が出力されたりする。人間の死体を生成させると必ずモザイクがかかるなど、AIの中での「適切さ」の基準も見えてきました。


左:「typical eye color」/右:「typical president」
AIには人間の営みが映り込んでいる
――テクノロジーを表現に使うことに関心を持ったきっかけは何だったのでしょうか。
報道写真家としてキャリアをスタートしていますが、私は写真をテクノロジーとして捉えています。芸術表現の一形式でありながら、テクノロジーと不可分に結びついている。写真技術の進化は常に表現の可能性を広げてきました。複写ができるようになったことで報道写真が発展し、カメラが小型化して戦争の最前線に持っていけるようになった。フィルムからデジタルになってまた表現が変化した。そうした発明の歴史の延長線上に生成AIがあると考えています。
――写真と生成AIが延長線上にあるというのは、意外な印象です。
生成AIの特徴的な点は、従来の写真が持っていた光学的な原理から解放されたことです。光学的な原理に基づく従来の“Photography”から、より自由な“Picture”の段階に入ってきた。海外のアートフェアでは、AIで生成された画像を“Promptgraphy”と呼び分けるようになってきています。また、これまで写真において、カメラをどこに向けるか、できた写真から何を読み取るかは、すべて人間が担ってきた役割でした。そこが機械に代替され始めたという感覚があります。AIが作り出す画像は“Photography”ではないかもしれないけど、写真という意味では、人類の営みが鏡として映り込んでいるような感覚を持っています。
――人間とAIは創作においてどのような関係になると考えていますか。
AIをアートに利用するか、その作品をアートと認めるかはアートの世界でもいろいろな意見があります。
私は人間とAIは相互補完的な関係にあると考えています。人間がテクノロジーを作り、デザインし、そしてまたテクノロジーによって人間がリデザインされるという、フィードバックループが存在している。私は積極的に自分をAIに投げ出し、ある種の共犯関係を作り出すことで面白い表現が生まれると考えています。
人間の知性には制約があります。その制約を超えるためにAIを使うことには大きな可能性がある。人間の知性では到達し得なかったところに、機械の力をステップとして跳躍していくことができるのではないでしょうか。
――AIによって大量のイメージが生み出される中で、それをアート作品として成立させる要素とは何でしょうか。
どれを見せるか、見せないか。それは、基本的に美学的な判断で決めています。その絵で人間が感動できるかどうかですね。私は最終的に、アートは人間の感動のためにあると考えています。作品を見たときに私自身が心を動かされるかどうか。AIが見立てたものを見て、私がまた新たな何かを見立ててしまう。そういった心の動きも大事にしています。
――最後に、今後の展望をお聞かせください。
まだ次の作品に向けて試している段階ですが、顔検出システムに、顔写真ではない画像を入力して、そこから顔を見つけ出させるという実験をしています。いわば、機械による心霊写真のようなものです。人間には、星空から星座を生み出したり、洞窟のひび割れに何かを見出したりする、「見立て」の能力があります。前作もそうですが、私はこうした人間の「見立て」の能力に関心があります。AIを通すことで、人間や世の中で起きていることを考えやすいという面があります。AIの基礎的な技術を学びながら、こうした探求を続けていきたいと考えています。
◆
この記事は、『AI白書2025 生成AIディション』(角川アスキー総合研究所刊)の転載です。最新版となる今年度のAI白書は「生成AIエディション」として、爆発的な進化を遂げる生成AIの開発や利用に欠かせない最前線の知識を徹底紹介。東京大学 松尾・岩澤研究室の協力のもと、最新の研究論文や、経済産業省の生成AI開発力強化プロジェクト「GENIAC」参加企業へのインタビューなどさまざまな調査を通じて、生成AIの技術や市場動向、法的論点など、AI社会の到来を見据えた視点で整理し解説します。詳しくは公式サイトをご覧ください。
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製
- 小橋川誠己 [Motoki Kobashigawa]日本版 編集者
- MITテクノロジーレビュー[日本版]副編集長(オペレーション担当)