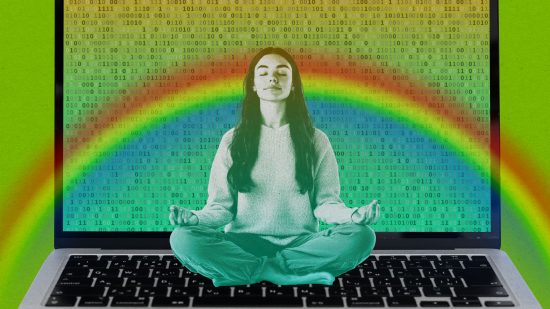起業?就職?大学に残る? 気鋭の若手研究者たちが本音で語り合った
これからの研究者人生をどう過ごすか? MITテクノロジーレビュー[日本版]と一般社団法人クロスユーのイベントで、気鋭の若手研究者らと大学院生らが議論を交わし、研究者のキャリア選択について考えを深めた。 by Yasuhiro Hatabe2025.02.18
研究機関としての大学の変化や、資金獲得方法の多様化、パラレルキャリア、大学発ベンチャーの活性化など、研究者を取り巻く環境が変化する中、その変化に適応する新しいキャリア戦略が、研究者に求められている。
2025年1月31日、MITテクノロジーレビュー[日本版]と一般社団法人クロスユーは、大学院生・ポスドク(博士研究員)など若手研究者のキャリア戦略を考えるイベント「U35イノベーターと考える研究者のキャリア戦略」を東京・日本橋のX-NIHONBASHI TOWERで開催した。
MITテクノロジーレビュー「35歳未満のイノベーター(Innovators Under 35 Japan)」の選出者から、スタートアップ、アカデミア、民間企業という異なる立場で活躍する3人の研究者をゲストに迎え、現在のキャリアを選択した経緯や研究環境などについて話し合った。
スタートアップからは、輝翠TECHの創業者兼CEOで、農業ロボットの研究開発を手掛けるブルーム・タミル氏。アカデミアからは、防衛大学校応用科学群応用化学科講師で、次世代ロケット推進剤を研究する松永浩貴氏。民間企業からは、NEC ビジュアルインテリジェンス研究所で、人工衛星画像の解析を研究する戴 岑容(タイ・サンジョン)氏が登壇した。3人による座談会、この日参加した若手研究者同士のグループ・ディスカッション、さらには登壇者と参加者との全体ディスカッションと、インタラクティブなイベントとなった当日の模様を紹介する。
【お知らせ】本イベントの第2弾が3月14日に開催決定! MITテクノロジーレビューのU35イノベーターから気鋭の研究者をゲストに迎え、研究者のキャリアについて考えます。詳細・申し込みはこちら。
現在のキャリアを選んだそれぞれの理由
座談会は、MITテクノロジーレビュー[日本版]副編集長の小橋川誠己がモデレーターを務めた。最初のテーマは、「現在のキャリアをなぜ、どうやって決めたのか」。
 横浜国立大学で物質工学を学び、ロケット推進剤や化学安全工学を専門とする松永氏は、「何よりも研究が楽しくなったことと、研究内容のデータも順調に出て論文が書けそうになり、研究で生計を立てられる見通しが立ったことが決め手でした」と研究職に進んだ経緯を語った。研究所かアカデミアかで迷ったものの、「後輩指導が好きだったこと、幼い頃の夢が学校の先生だったこと」も踏まえて大学教員の道を選んだという。松永氏は博士号取得後に私立大学で助教を務め、2023年から防衛大学校に移っている。
横浜国立大学で物質工学を学び、ロケット推進剤や化学安全工学を専門とする松永氏は、「何よりも研究が楽しくなったことと、研究内容のデータも順調に出て論文が書けそうになり、研究で生計を立てられる見通しが立ったことが決め手でした」と研究職に進んだ経緯を語った。研究所かアカデミアかで迷ったものの、「後輩指導が好きだったこと、幼い頃の夢が学校の先生だったこと」も踏まえて大学教員の道を選んだという。松永氏は博士号取得後に私立大学で助教を務め、2023年から防衛大学校に移っている。
宇宙ロボットの研究で著名な吉田和哉教授率いる東北大学の研究室で月面ローバーを研究していたタミル氏は、「もともとは宇宙工学分野を専門にしたいと考え、実際に博士課程まで進みました。修士課程まではロボット制御を研究し、博士課程では人工知能(AI)に研究テーマを移しましたが、その頃から専門知識を深めたいという思いが強かった」と振り返った。宇宙から地上の「農業」にテーマを移し、スタートアップを起業したのは「学生時代に東北地方を旅して回った中で、農業分野でのロボット実装に興味を持ち、農家の課題解決に取り組みたいと考えたから」だという。

撮影:曽根田 元
戴氏は香港大学・香港科技大学大学院でコンピューター科学を学び、2019年にNECに入社した。「最先端の技術を生かすことで、想像を超えるものをつくることに魅力を感じた。問題解決への興味と、『学び続けたい』という思いから研究職を志望しました」という。民間企業を選んだ理由は、「社会実装に近いところまで関わる機会と、開発サイクルが速く、トライ&エラーがしやすい環境、そして幅広い業種とのコラボレーションの可能性があるため」。一方、「大学教員には学生を指導する能力が求められること、スタートアップでは事業を切り拓く野心や社交性が求められる点が、自分の性格とは少し違う」と考えたことも、現在の道を選択した理由だと明かした。
スタートアップ、アカデミア、民間企業の研究環境
その後、座談会の話題は「現在のキャリア、研究環境の良い点」に移った。
タミル氏はまず、「企業は大学や研究機関よりもリソースを多く持っており、社会実装を目指す上で魅力」としたうえで、就職ではなくスタートアップを選択した理由として、「宇宙産業の既存企業では顧客が限定的であること、SpaceXでのインターン経験を通じてスタートアップ文化に共感したこと」を挙げた。「フラットな組織構造と迅速な意思決定ができる環境に魅力を感じ、自身でスタートアップを立ち上げました」。
戴氏は大手企業が持つリソースの豊富さを挙げた。「優れた人材にアクセスできるのは大きな利点です。例えば、当社には顔認証の分野で世界的に著名な研究者がいますが、そうした方から直接アドバイスを受けられることはメリット。また、政府や他の大手企業と良好な関係が構築されているため、さまざまなプロジェクトに参加できたり、資金調達がスムーズにできたりすることも魅力」。大企業では部署による「分業」が確立されていることが多いが、この点が「研究開発に専念できる環境」につながっているという。一方で、異なる分野の専門家との社内交流の機会もあるといい、「幅広い知見を得られる機会があるのが、民間企業の良い点だと思います」と話した。

撮影:曽根田 元
アカデミアの魅力について松永氏は、「研究と教育の両方を担うこと」だとした。「皆さんのような優秀な学生を世に送り出すことで社会に貢献できる。そこに大きなやりがいを感じています」。加えて、研究室を運営するおもしろさもあるという。「柔らかい発想を持つ学生たちとのディスカッションを通じて新しい視点を得ることや、そこからイノベーションが生まれるのが楽しい」。さらに、「研究面での自由度が高いこと」も良い点だと指摘する。「大学では基礎研究に重点が置かれますが、研究の方向性や資金調達、テーマ設定など、すべてを自分で一から組み立てていける点にやりがいがある」と松永氏は続けた。
スタートアップに“コネ”は必要ではない
座談会の後は、当日イベントに参加した若手研究者が3つのグループに分かれてディスカションを実施した。各グループは、研究者たちの現在の所属にかかわらずランダムに編成され、「スタートアップ」「アカデミア」「民間企業」それぞれに進む立場になったつもりで、座談会の感想を述べ合う。その後、グループごとに登壇者へ聞きたい内容を整理し、全体ディスカッションで発表する「4つの質問」を決定する流れで進められた。

撮影:曽根田 元
ディスカッションでの各グループと登壇者とのおもなやり取りを以下で紹介する。まずは、タミル氏が回答したスタートアップについての質問からだ。
Q. 「どのようなメンバーで起業したのか」「スタートアップを成功させるには、どのようなコネがあるとよいのか」
「創業時は、仲の良かった1人の先輩と立ち上げました。その後は開発を進めながら、日本語学校で一緒に勉強していた友人に参加してもらったり、フェイスブックでPRして人づてに仲間を集めたりしました。政府関係者などとコネがあるに越したことはありません。でも、そうしたつながりがなくても、自分でがんばって人脈を作っていった方が最終的には成功できると思います」
Q.「スタートアップが目指すゴールはどこなのか、アカデミアにいたときとどのように違うのか」
「輝翠TECHは今、アーリーステージの企業として、資金調達や政府からの補助金などで事業運営している状態。ロボットやWebのシステム開発に、今後10〜15年の長期的な技術開発が必要ですが、徐々に成長させ、売上だけで事業が回る状態を目指しています。将来的には日本国内だけでなく、海外展開も視野に入れています。また、ゆくゆくは農業以外にも対象分野を広げて、ロボットの社会実装するを目指しています。これは、大学院時代に抱いていたビジョンともそれほど違いません。その理想に向かって着実に歩みを進めている状況です」
アカデミアを選ぶ上での経済的な懸念は?
続いて、アカデミアについての質問。これには松永氏が答えた。
Q. 「進路を決める際に、もしポストが空いていなくともアカデミアに残っていたと思うか」
「早い時期からどのようなポストがあるのかを広くチェックしていました。私の専門の『安全工学』というキーワードで調べてもほとんど公募はありませんが、『化学』で調べると多数の公募が見つかります。少しでも関係があるところには積極的に応募し、結果としてアカデミアの職を得ることができました。博士課程での指導教員からは、ポストが見つからなかった時にはポスドクとして研究室に1〜2年いてもよいと言われていたので、もしそうなったらポスドクに進んでいたと思います。それもない場合は、学会などで知り合った民間企業の方からのお誘いがあったので、そちらに就職していたかもしれません」
Q. 「アカデミアに行くと決めた際に、経済的な不安はなかったか」
「確かに民間企業と比べると給与水準は低いかもしれませんが、研究を続けたいという思いが最優先でした。周囲のポスドク研究者も経済的に困っている人はいませんでしたので、収入面の不安はそれほどありませんでした」
Q. 「もし社会実装に近い分野であれば、起業家精神を持っていたか」「大学外での副業について考えているか」
「私の専門である安全工学が必ずしも社会実装から遠いわけではないと思いますが、自分でイノベーションを起こしてモノを作っていく分野ではないので、起業という選択肢はあまり考えていませんでした。ただ、大学内には副業でベンチャー企業を経営している先生も数多くいますので、研究分野によっては起業の可能性はあったかもしれません」
「私自身がこれまで勤務した職場は副業禁止だったため、外部講師としての講演料以外の副収入を得る機会は限られていました。ただ、近年は多くの大学が副業を許可する方向に変わってきているので、副業で収入を得る可能性はあると思います」

撮影:曽根田 元
「企業に求められる研究」と「自分がしたい研究」の狭間で
最後は、民間企業に関する質問。戴氏が回答した。
Q. 「プロジェクト単位で、どれくらい自分の好きな研究ができているのか」
「民間企業かどうかではなく、会社や直属の上司によって大きく変わってくると思います。例えば、私の所属するAIグループに入社した同僚は希望と異なるプロジェクトに配属されましたが、上司から別の研究テーマの提案を求められ、今では自分のアイデアをPoC(概念実証)の段階まで進めているところです」
「私自身はAIグループで働いており、これまでの経験・バックグラウンドを生かせる環境で仕事に取り組めています。ただ、企業の求める製品開発と私個人の研究志向との間で時にギャップを感じ、モチベーションが変わることはあります。企業のビジョンと連動する形で取り組んで行く必要があると思っています」
Q. 「民間企業において、研究の社会実装に対してどれだけ興味を持った方がいいのか」「自身の専門性や、研究に対する興味とプロジェクトとの相違をどこまで許容できるか」
「私が務める会社は非常にカスタマー・オリエンテッドで、利益も重視されています。そのため、短期的な利益創出を目指す研究が求められます。一方で、短期的な成果を求められない未来志向型の研究にも取り組んでいます。上司に研究テーマを提案して上手く説得できれば、長期的な視点での研究も可能です。そのような文化を持つ会社を探すことも、研究職のキャリアを考える上で一つの有効な手段だと思います」
「民間企業にはさまざまなプロジェクトありますので、一時的に自分の専門分野と重なる部分が小さいプロジェクトに配属されても、新しいプロジェクトが立ち上がってきたときにチャレンジできることは魅力だと感じています」
◆
ディスカッションの最後には、3人のイノベーターからの参加者へ向けたメッセージが語られた。それぞれ言葉は違うものの、立場にかかわらず「やりたい研究をしてください」というのが共通するメッセージだ。どのようなキャリアを選ぶにしても、研究者として活躍していく上では、まず本気で取り組みたい研究テーマを見つけることが前提となる。
終了後の懇親会では予定時間を過ぎても話が途切れず、積極的な意見交換が行われた。所属も研究分野も異なる参加者同士が新しい視点を取り入れながら、これからの研究者人生をどう過ごすか、考えを巡らせるイベントとなった。

3月14日に第2弾を開催します

【お知らせ】本イベントの第2弾を3月14日に開催します。 宇宙スタートアップ経営者、ウェアラブル・デバイス研究者、AIロボット研究者をゲストに、研究者のキャリアについて考えます。参加は無料。詳細・申し込みはこちら。
- 人気の記事ランキング
-
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製
- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者
- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。