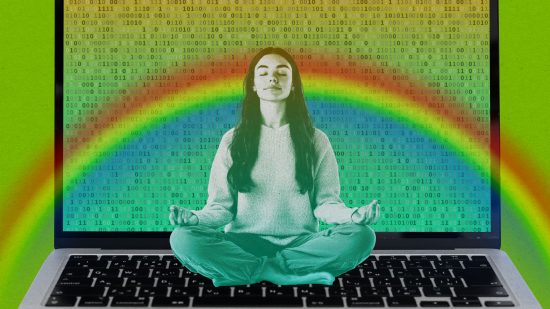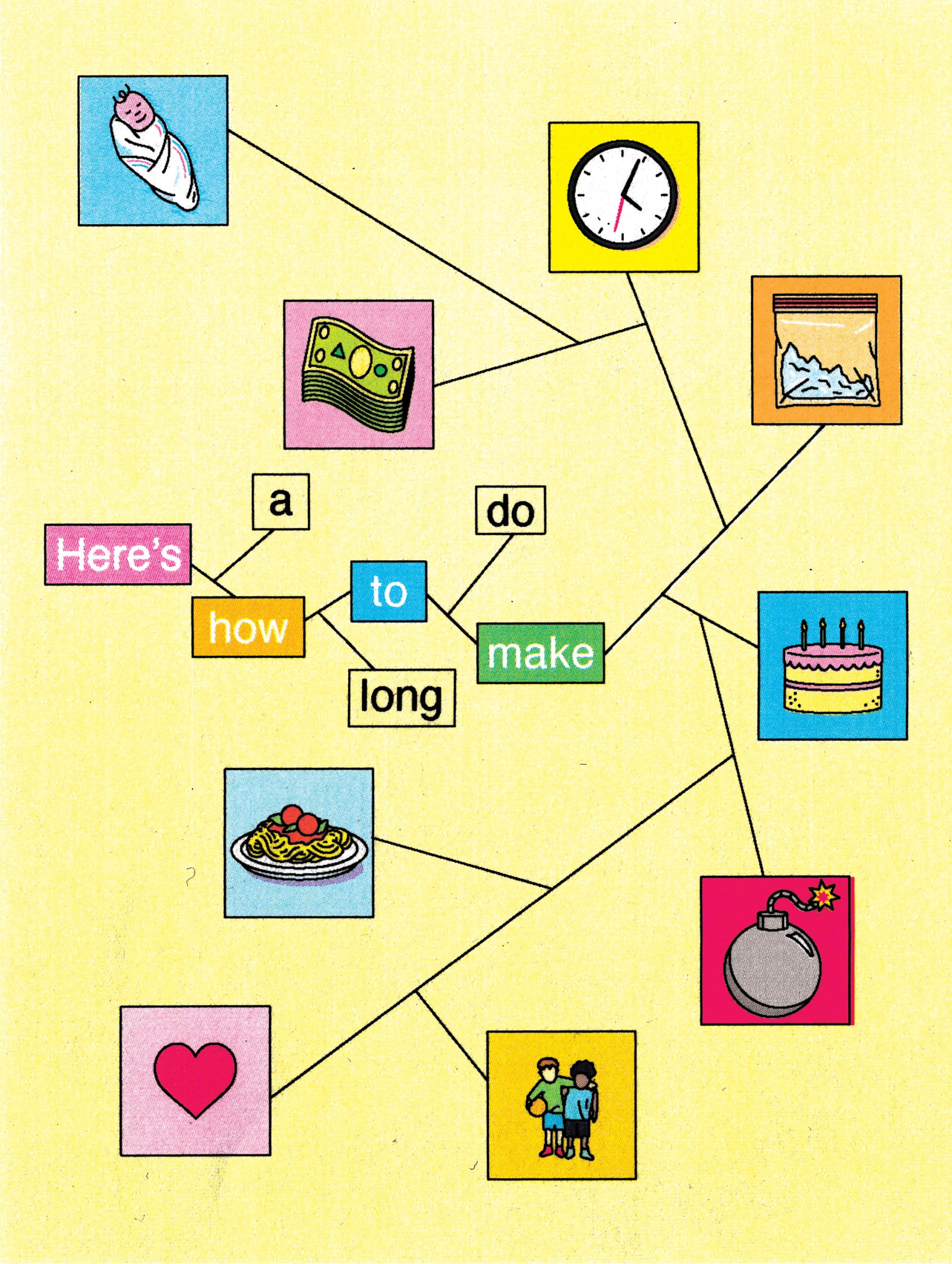
「ググる」時代の終わり、
世界の知識を解き放つ
生成AI検索がもたらすもの
インターネット検索エンジンは情報へのアクセス方法を革新し、25年にわたって私たちの生活を支えてきた。しかし今、グーグルをはじめとするテック企業は生成AIを活用した新しい検索体験を模索している。単なる進化ではなく、AIは世界中のすべての知識を呼び出す新しい方法を解き放つ可能性がある。 by Mat Honan2025.01.17
- この記事の3つのポイント
-
- グーグルやオープンAIなどが生成AIを用いた検索機能を開発している
- 生成AIを活用した検索は従来とは全く異なる体験をもたらす
- 生成AI検索は情報統合により新たな価値を生むが課題も多い
私たちは皆、俗に言う「ググる」の意味を知っている。検索ボックスの中に関連する単語をいくつか入力すると、最も関連性の高い結果につながる青いリンクが一覧表示される。もしかすると、一番上に簡単な説明がいくつか表示されるかもしれない。地図や、スポーツの試合結果、動画が表示されることもあるだろう。それらは基本的に、インターネット上にすでに存在する情報を取得し、ある種の構造化された方法で示しているに過ぎない。
だが、そのすべてが変わる可能性がある。私たちは今、新たな変曲点に立っている。
1990年代以来、検索エンジンが私たちに情報を提供してきた方法に、今、最大の変化が起きている。キーワード検索はもう不要になる。どのリンクをクリックすればよいか、選別する必要もなくなる。その代わりに私たちは、会話型検索の時代に突入しようとしている。つまり、キーワードの代わりに、自然言語で表現された具体的な質問を用いるのだ。そしてリンクの代わりに、生成AIの書いた回答が表示されることが、ますます増えていく。回答はインターネット全体から得られる生きた情報に基づいて作成され、これまでと同じ方法で提供されることになる。
もちろん、過去25年間にわたって検索のあり方を決定づけてきたグーグルは、この変化の先頭を走ろうとしている。2023年5月、グーグルは検索クエリに対してAIが回答を生成するテストを開始した。自社の大規模言語モデル(LLM)を活用し、専門家や信頼できる友人から得られるような回答を提供する仕組みだ。グーグルはこれを「AIによる概要(AI Overviews)」と呼んでいる。グーグルのサンダー・ピチャイ最高経営責任者(CEO)はこの仕組みについて、「私たちが非常に長期にわたって検索に対して加えてきた変化の中でも、最も前向きなものの一つです」とMITテクノロジーレビューの取材に語った。
「AIによる概要」は、グーグルが対処できるクエリの種類を根本的に変える。例えば、こんな風に質問できるようになった。「来月、1週間、日本に行きます。東京に滞在しますが、何回か日帰り旅行もしたいです。近くでお祭りはありますか? 鎌倉でサーフィンをするのはどうでしょう? よいバンドの演奏はありますか?」すると、レディット(Reddit)へのリンクだけでなく、最新の情報で作り込まれた回答が得られるはずだ。
さらに重要なのは、かつてはほぼ不可能に近かった検索を試してみても、適切な回答を得られることだ。どんなことを探しているのか、正確に説明できる必要はない。庭にいる鳥の見た目や、冷蔵庫で起きている問題、車が発している奇妙なノイズなどを説明できれば、以前ならインターネットのあちらこちらに散在していた情報源からまとめ上げられた、まるで人が話しているような説明を得ることができる。驚くべき体験であり、一度この方法で検索を始めると、病みつきになってしまう。
こうした変化はグーグルだけのことではない。オープンAIのChatGPT(チャットGPT)もWebにアクセスできるようになり、クエリに対する最新の回答を見つけるのがはるかに上手になった。マイクロソフトは2024年9月、Bing(ビング)に生成検索機能を正式に搭載した。メタ(Meta)も独自の生成検索を開発している。スタートアップ企業のパープレキシティ(Perplexity)もまた、「すばやく動き、破壊せよ(move fast, break things)」の精神のもと、同様の取り組みを進めている。それらの企業が、次の主要な情報検索プラットフォーム、つまり「次のグーグル」になろうと競い合い、文字どおり数兆ドルの価値を生み出す競争が勃発している。
ただ、誰もがこの変化を歓迎しているわけではない。パブリッシャー(コンテンツ供給者)は完全に恐怖を抱いている。「ゼロクリック」の未来への懸念が高まっているからだ。この未来では、グーグル登場以前からWebの基盤だった検索のリファラル・トラフィックが完全に消滅してしまうかもしれない。
昨年6月、スマートフォンのPerplexityのアプリからプッシュ通知が届いたとき、私はそんな未来の一端を垣間見る経験をした。パープレキシティはWeb検索を再発明しようとしているスタートアップ企業である。しかし同社のアプリは、検索クエリに対して回答を提供するだけでなく、さまざまな情報源からAIがまとめ上げた、その日のニュースに関する記事全体を作成する機能も備えている。
その日、Perplexityのアプリは、エリック・シュミット(グーグル元会長)が新たに立ち上げたドローン企業に関する記事をプッシュ配信してきた。その記事には見覚えがあった。同じ週にフォーブス(Forbes)誌がスクープした、有料会員限定の記事だった。だが、Perplexityの記事に掲載されていた画像は、フォーブスの記事の画像と同一に見えた。文章も記事の構成もかなり似ていた。実質的に同じ記事が、無料で公開されていたのだ。私は元の記事の編集を担当した友人にメールを送り、フォーブスがパープレキシティとコンテンツの再配信契約を結んでいるかどうか確認した。契約はしていなかった。友人はショックを受け、激怒し、困惑した。そのような思いをしたのは、この友人だけではない。現在、フォーブス、ニューヨーク・タイムズ、およびコンデナストの3社は、パープレキシティに対して停止措置命令の通知を送っている。ニューズ・コープ(News Corp)は、損害賠償請求訴訟を起こしている。
それはまさに、パブリッシャーたちが恐れてきた悪夢のシナリオだった。AIがパブリッシャーの有料コンテンツを収集し、再パッケージ化して、元のコンテンツをクリックする理由をまったく残さない方法で自らのオーディエンスに提示していたのだ。実際、パープレキシティは「概要」ページで、この検索エンジンを選ぶ理由として、「リンクをスキップする」ことを挙げている。
しかしこれは、パブリッシャーや、あるいは私自身の利益だけに関わる問題ではない。
LLMのもたらすこれらの新たな結果が、私たちの基本的な共有現実にとって何を意味するのか、人々は懸念している。言語モデルは虚偽の情報をでっち上げる傾向を持ち、ときに馬鹿げた幻覚(ハルシネーション)を見ることもある。さらに生成AIは、同じ質問に対して毎回まったく異なる新しい回答を提供したり、異なる人に回答する際に、その人に関する知識に基づいて異なる答えを提供したりすることもある。生成AIによって、「定型的な正解」という概念は消滅する可能性があるのだ。
しかし、間違いなく、これが検索の未来だ。自分で少し試してみればそのことが実感できるはずだ。
確かに、私たちはこれからも常に、検索エンジンを使ってWebをたどり、新しく興味深い情報源を発見したいと考えるだろう。しかし、リンクの役割は徐々に後退している。AIが、Webの至るところから集めたリアルタイムのデータを使い、ほぼすべての種類の質問に対して理路整然とした回答をまとめられるようになったことで、従来よりも優れた検索体験が実現されつつある。特にここ数年でWeb検索が陥ってきた状態と比較すると、その違いは明白だ。Web検索は完全に機能しなくなったわけではないが(データによるとグーグル検索の利用頻度は過去最高を記録している)、少なくともますます乱雑になり、使いにくくなっている。
必要な情報を見つけるために検索エンジンの言語を話さなければならないなんて、誰が望むだろうか? 明確な答えがすぐに得られるのに、わざわざリンクをたどる必要があるだろうか? もっと言えば、ただ「知る」だけで済むのなら、知識を得るためにわざわざ「学ぶ」ことを人々は望むのだろうか?
始まりは「Archie(アーキー)」だった。初の本格的なインターネット検索エンジンだったArchieは、それまでリモートサーバーの奥深くに隠されていたファイルをクロールした。しかし、教えてくれるのはファイル名だけで、その中に何があるのかはわからなかった。画像をプレビューする機能もなければ、検索結果の階層構造もなく、大したインターフェイスすらなかった。しかし、それが始まりだった。そして、それは十分に優れたものだった。
その後、ティム・バーナーズ=リーがワールド・ワイド・Web(WWW)を生み出し、あらゆる種類のWebページが次々と誕生していった。モザイク(Mosaic)のホームページ、インターネット・ムービー・データベース(IMDb)、ジオシティーズ、ハンプスター・ダンス、ウェブリング、サロン(Salon)、イーベイ(eBay)、CNN、連邦政府各機関のサイト、それにトルコの誰かの個人ホームページ——。
やがて、あまりに多くのWebページが存在するようになり、どこから手をつければよいのかさえわからなくなってしまった。インターネットを効率よくたどって必要な情報を実際に見つけるための、より優れた方法が切実に求められていた。
1994年、ジェリー・ヤンが、「Yahoo!(ヤフー)」を作った。Webサイトを分類する階層型ディレクトリであるYahoo!はすぐに、何百万人もの人々のホームページとなった。Yahoo!は実際のところ、それなりに良いものだった。正直に言って今振り返ると、当時は誰もが実際よりもずっとよいものだと思い込んでいたように思う。
Webはさらに成長を続け、不規則に拡大し、日々膨大な情報をネットにもたらした。すると単なるカテゴリー別のサイトリストではなく、実際にそのすべての中身を見てインデックス化してくれる仕組みが必要だった。90年代後半までにはWeb検索は、さまざまな検索エンジンを選んで使うことを意味するようになった。「AltaVista(アルタビスタ)」「AlltheWeb(オールザウェブ)」「WebCrawler(ウェブクローラー)」「HotBot(ホットボット)」などだ。それらは従来のWeb検索よりも大幅に改善されており、少なくとも最初のうちは優れていた。
検索エンジンが普及するにつれ、トラフィックをもたらす検索エンジンの力を利用しようとする最初の試みも出現した。貴重で価値のあるトラフィックを、Webパブリッシャーは広告収益のために頼りにし、小売業者は商品を見てもらうために利用した。それは時に、検索結果の順位を押し上げるためだけに考案されたキーワードや無意味なテキストを、ページ内に詰め込むことを意味した。状況はかなり悪化した。
そして、グーグルが登場した。1998年に登場したグーグルは、大げさに表現するのが難しいほど革命的だった。グーグルは単にWebページのコンテンツをスキャンするだけでなく、そのページにリンクを張っている元のサイトまで分析した。これにより、Webサイト同士の関連性を評価できるようになった。ごく単純化して言えば、他のサイトからより多く引用されているWebページほど、グーグルによって信頼性が高いと判断され、検索結果の上位に表示されるようになった。このブレークスルーにより、グーグルは、検索結果の関連性を向上させる点で、それまでのどの検索エンジンよりも飛躍的に優れたものとなった。それはまさに驚異的だった。
25年間にわたり、グーグルは検索を支配してきた。ほとんどの人にとって、グーグルこそが「検索そのもの」だった(その支配的な地位の範囲は、現在、米国と欧州連合で複数の法的調査の対象となっている)。
しかし、グーグルは長年にわたり、単なる青色のリンクリストの提供からの脱却を進めてきたと、同社で検索担当主任科学者を務めるパンドゥ・ナヤックは指摘する。
「いわゆるWeb検索結果だけではなく、画像や動画、そしてニュースに関する特別な情報もあります。直接的な回答や辞書的な回答、スポーツの結果、ナレッジグラフ付きの回答、強調スニペットといったものもあります」とナヤック主任は言い、グーグルが質問に対してより直接的に回答するために講じてきた、さまざまな手法を列挙した。
それは事実だ。グーグルは長い時間をかけて進化を重ね、答えを提供するポータルとしての地位をますます強固なものにしてきた。グーグルは、人々が答えを得るためにWebサイトへ誘導されるのではなく、試合速報や …
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製