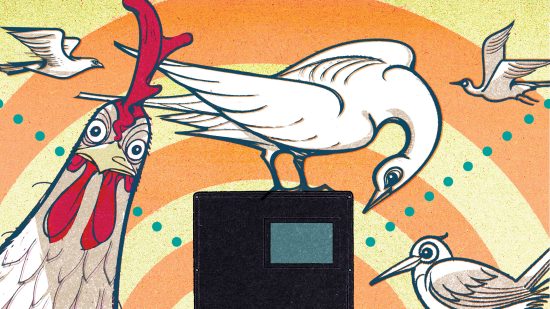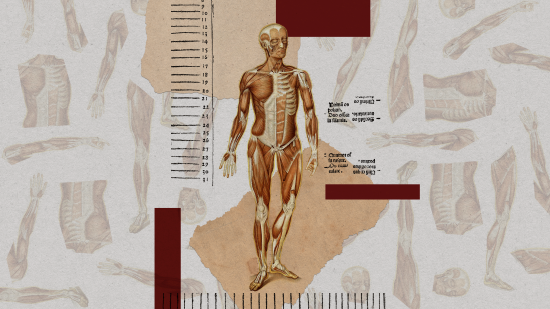SNSに「有害ラベル」を、 米公衆衛生局長官の主張の根拠は?
ソーシャルメディアには健康への害を示す警告文を表示するべき、と主張する米公衆衛生局長官の記事が米紙に掲載された。直感的に共感する人も多そうだが、明確なエビデンスがないこともまた事実だ。 by Jessica Hamzelou2024.06.28
- この記事の3つのポイント
-
- 米公衆衛生局長官がSNSへの有害ラベル表示を提案
- 青少年の健康被害への影響を示すエビデンスは限定的
- SNSの潜在的な害への対策とし警告以外の方法もある
この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。
6月17日、「国民の医者」の呼び名で知られる米国の公衆衛生局長官が、ソーシャルメディアには健康への害を示す警告文を表示するべきであると主張する論説文を発表した。その目的は、ティーンエイジャーを有害な影響から守ることだ。「ソーシャルメディアに1日3時間以上費やす青少年は、不安やうつ症状のリスクが2倍になる」と、ビベック・マーシー長官はニューヨーク・タイムズ紙に掲載された論説文の中で述べ、「さらに、青少年の半数近くがソーシャルメディアのせいで体調の悪化を感じると答えている」と書いた。
私はマーシー長官の懸念に対し、本能的に共感する。私は30代後半ではあるが、インスタグラムをちょっと見ただけで、すごく気分が悪くなってしまうことがある。私には2人の幼い娘がおり、彼女たちが思春期になって同級生が使っているソーシャルメディア・サイトにアクセスしたいと言い出したら、どう対応すればいいのか心配だ。子どもたちはすでに携帯電話に引き付けられている。もうすぐ6歳になる長女は、明け方によく私の寝室へやってきて夫の携帯電話を見つけ、どうにかして「ハッピー・クリスマス(戦争は終わった)」を大音量で流す方法を見つけ出す。
しかし、ソーシャルメディアと健康との間に、白黒がはっきりつくような関係性がないことも私は知っている。ソーシャルメディアは、ユーザーにさまざまな方法で影響を与える可能性があり、ポジティブな影響を与えることもしばしばだ。そこで、懸念されること、その背後にあるエビデンス、そしてそれらの問題に取り組む最善の方法を詳しく見てみよう。
もちろん、マーシー長官の懸念は新しいものではない。実際、新しい技術が導入されるときは常に、その潜在的な危険性を警告する人がいるものだ。印刷機、ラジオ、テレビなど、かつてのイノベーションにはすべて批判者がいた。2009年に英国のデイリー・メール(Daily Mail)紙は、フェイスブックの使用とがんを関連づけた。
もっと最近では、ソーシャルメディアに関する懸念の中心は若者だ。10代には多くのことが起こる。脳が成熟し、ホルモンが変化し、他者との新しい関係の築き方を模索する。この時期は、メンタルヘルス障害にもかかりやすくなると考えられている。世界保健機関(WHO)によれば、こうした障害の約半数は14歳までに発症すると考えられており、15歳から19歳の4番目に多い死因は自殺である。この状況はソーシャルメディアによって悪化する一方であると、多くの人が主張してきた。
たとえば、ネットいじめ、暴力的または有害なコンテンツへの曝露、非現実的な身体基準の促進などが、気分の低下や不安・うつ病などの障害の主要な引き金になる可能性があると、さまざまな報告書で言及されてきた。また、ソーシャルメディアの使用と関連した自傷行為や自殺の目立った事例がいくつかあり、多くの場合、ネットでのいじめや虐待が関係していた。ちょうど今週、インドのケララ州で起きた18歳の自殺は、ネットいじめに関連するものだった。また、有毒物質の吸入、激辛トルティーヤチップスの摂取、自らの窒息など、ソーシャルメディア上で流行した危険なオンラインチャレンジに参加して死亡した子どもたちもいる。
マーシー長官の今回の論説文は、公衆衛生局が2023年公表した、ソーシャルメディアと青少年のメンタルヘルスに関する勧告に続くものだ。ソーシャルメディアを使用する既知のメリットと害のいくつか、および「未知の影響」が示されたその25ページの文書は、ソーシャルメディアに対する健康問題としての認識を高めることを目的に作成された。問題は、物事が完全には明確になっていないことである。
「現在のところ、エビデンスはかなり限られています」と、ソーシャルメディアが若者のメンタルヘルスに与える影響を研究するユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究者、ルース・プラケット博士は述べる。ソーシャルメディアとメンタルヘルスに関する研究の多くは、相関的なものだ。ソーシャルメディアの利用がメンタルヘルス障害を「引き起こす」ことを示すものではないと、プラケット博士は言う。
公衆衛生局の勧告は、これらの相関研究の一部を引用している。また、2000年代半ばのフェイスブック導入後の大学生の精神的健康状態に注目した研究など、調査に基づくいくつかの研究も指摘している。しかし、フェイスブックが学生のメンタルヘルスに悪影響を与えたという執筆者の結論を受け入れるとしても、他のソーシャルメディア・プラットフォームが他の若者たちに同じ影響を与えるとは限らない。フェイスブックとその使い方も、この20年でずいぶん変わっている。
ソーシャルメディアはメンタルヘルスに影響を与えないという結果が示された研究もある。昨年発表された研究では、プラケット博士の研究チームが英国の3228人の子どもたちを対象に、ソーシャルメディアの利用と精神的健康状態が時間の経過とともにどう変化するかを調査した。子どもたちが12歳から13歳のときに最初の調査が実施され、14歳から15歳のときに再び調査が実施された。
プラケット博士は、ソーシャルメディアの利用が年若い参加者たちに害を及ぼすだろうと予想していた。しかし、2回目の調査をしたところ、そうではないことがわかった。「ソーシャルメディアに費やした時間と、2年後の精神的健康状態の結果とは、関係がありませんでした」と、プラケット博士は話す。
他の研究では、ソーシャルメディアの利用が若者、特にマイノリティグループの若者にとって有益な場合があることが示されている。孤独を避け、仲間との関係性を強化し、自分のアイデンティティを表現する安全な場所を見つけるのに役立つことがあると、プラケット博士は言う。ソーシャルメディアは社交のためだけのものではないのだ。今日の若者は、ニュースや娯楽、学校、さらには(インフルエンサーの場合は)ビジネスのためにこれらのプラットフォームを利用している。
「さまざまなエビデンスが混在しています。今のところ、重要な結論を出すのは難しいでしょう」(プラケット博士)。
マーシー長官は論説文の中で、「ソーシャルメディアは青少年の重大な精神健康被害と関連しています」と表示された警告ラベルをソーシャルメディア・プラットフォームに掲げることを求めている。
しかし、マーシー長官はタバコ製品の警告ラベルの効果を比較対象に挙げているが、ソーシャルメディアへの熱中に、タバコのチェーンスモークのような健康リスクはない。タバコが歯周病、肺気腫、肺がんなどさまざまな病気と関連していることを示す強力なエビデンスはたくさんある。喫煙が人の平均寿命を縮める可能性があることもわかっている。あのデイリー・メール紙の記事で何が書かれていたにしても、ソーシャルメディアについてタバコと同じような主張をすることはできない。
もっとも、マーシー長官自身が認めているように、健康被害警告がソーシャルメディアの使用に関連する潜在的な害を防ぐ唯一の方法ではない。まず、テック企業は暴力的で有害なコンテンツの削減や排除をさらに進めることができるかもしれない。デジタルリテラシー教育は、さまざまなソーシャルメディア・プラットフォームの設定を変更して子どもたちが目にするコンテンツをよりよくコントロールする方法を子どもたちとその保護者に知らせたり、画面に表示してもよいコンテンツを評価する方法を教えたりするのに役立つ可能性がある。
それらの対策はよさそうに思える。早朝のクリスマスソングに終止符を打つのにも役立つかもしれない。
MITテクノロジーレビューの関連記事
インターネットを子どもたちにとってより安全なものにするための法案が、米国の各州で相次いで提出されている。しかし、本誌のテイト・ライアン=モズレー記者(当時)が調査したように、各州のアプローチは異なっており、その結果、全体像に混乱が生じている。
米国の数十州が昨年10月にフェイスブックの運営会社であるメタを提訴した。本誌が当時報じたように、各州は、メタが承知の上で若いユーザーに害を与え、安全機能や有害なコンテンツについて誤解を招かせ、子どものプライバシーに関する法律に違反していると主張した。
中国は子どもたちのインターネット利用に対し、徐々に管理を厳格化してきた。昨年8月、中国のサイバースペース管理当局は詳細なガイドラインを発表した。その中には、たとえば8歳未満の子どものスマートデバイスの利用を1日40分までに制限するルールなどが盛り込まれた。さらに、子どものスマートデバイスの利用は、「初等教育、趣味や興味、一般教養教育」に関するコンテンツに限られる。本誌の中国担当記者であるヤン・ズェイが以前の記事でこの話を紹介している。
昨年、ティックトック(TikTok)が、18歳未満のユーザーに対して1日60分の利用制限を設けた。しかし、ズェイ記者が昨年3月に書いたように、中国版ティックトックである「ドウイン(Douyin:抖音)」では、さらに厳しい管理が実施されている。
ソーシャルメディアが若者に利益をもたらすことができる方法の1つとして、若者が安全な空間で自分のアイデンティティを表現できるようにすることがある。エリザベス・アン・ブラウンが2022年に書いたように、人の外見を表面的に変えてより女性的または男性的にするフィルターは、トランスジェンダーの人々がジェンダー表現について気軽にあれこれ試すのに役立つ可能性がある。アン・ブラウンは30代前半のトランスジェンダー女性、ジョシーの言葉を引用している。「スナップチャットのガール・フィルターは、抑圧された10年から解放されるための、最後の一撃でした」と、ジョシーは述べている。「鏡に映る自分よりも、自分らしい姿を発見しました。もう戻ることはできません」。
医学・生物工学関連の注目ニュース
- 優しい衝撃波は心臓組織の再生に役立つ可能性があるのか?「宇宙ヘアドライヤー」とも呼ばれるものの試験で、この治療法がバイパス手術からの回復に役立つ可能性が示唆されている。(BBC)
- 「中国で発生したこのウイルスで今、何が起こっているのかわかりません」。アンソニー・ファウチ(元米国立アレルギー感染症研究所所長)が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの最初の3カ月について、内幕を説明している。(アトランティック)
- マイクロプラスチックはどこにでも存在する。科学者たちが男性のペニスからマイクロプラスチックを発見するのも、時間の問題だった。(ガーディアン)
- 人工知能(AI)が人間の知性を上回るシンギュラリティ(技術的特異点)はより近づいているのか? レイ・カーツワイルはそう信じている。カーツワイルはまた、医療用ナノボットにより私たちは120歳を超えて生きられるようになると考えている。(ワイアード)
- 人気の記事ランキング
-
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- China built hundreds of AI data centers to catch the AI boom. Now many stand unused. AIデータセンター 中国でバブル崩壊か? 需要低迷で大量放置の実態
- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請
- How 3D printing could make better cooling systems 3Dプリントで製造の制約を解放、高効率な熱交換器が設計可能に
- ジェシカ・ヘンゼロー [Jessica Hamzelou]米国版 生物医学担当上級記者
- 生物医学と生物工学を担当する上級記者。MITテクノロジーレビュー入社以前は、ニューサイエンティスト(New Scientist)誌で健康・医療科学担当記者を務めた。