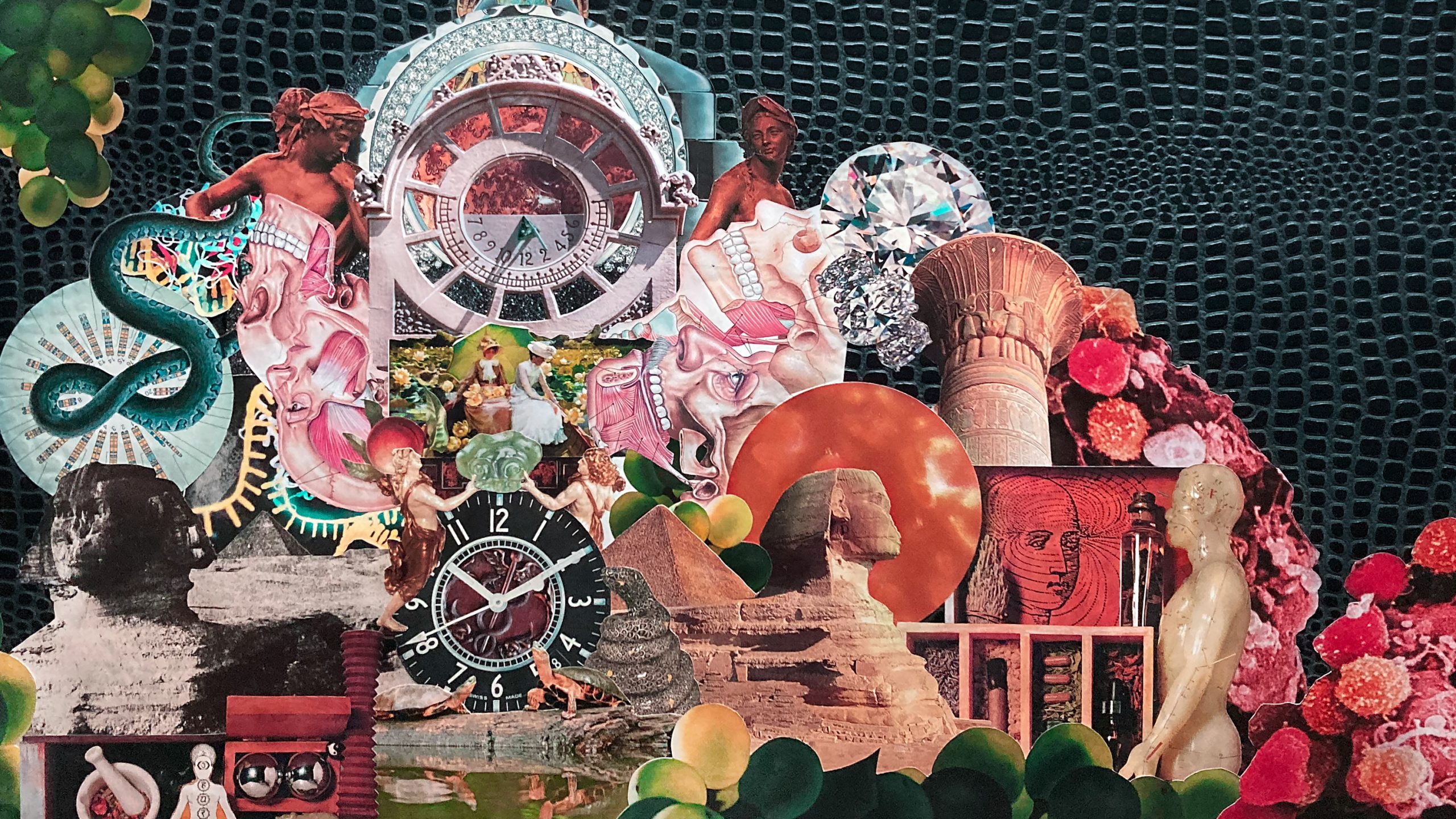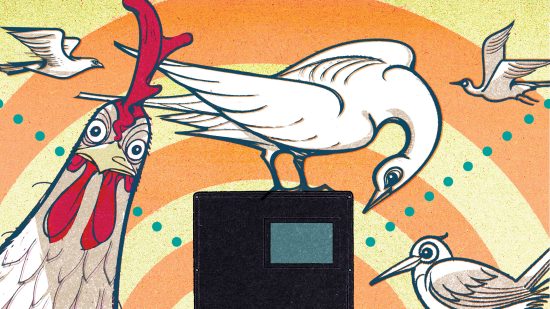長寿医学の探求、
「金持ちの道楽」から
正当な医療になり得るか
長寿クリニックは、主に富裕層を対象にさまざまな高額なサービスを提供しており、なかには怪しげなものもある。最近では、長寿医学の治療行為を正当な医学分野として確立し、ゆくゆくは大衆化させようとする動きが出てきた。 by Jessica Hamzelou2024.04.03
昨年12月のある晴れた肌寒い日、大勢の医師や科学者が、カリフォルニア州ノバトの丘の上に建つ研究所に集まった。健康長寿の専門家たちのグループが直接顔を合わせるのは初めてで、共有すべきことは山ほどあった。
このグループの目標は、人間の寿命を延ばし、かつその延ばした年数を良い健康状態で過ごせるようにすることだ。しかし、今回の会議の参加者には別の目標もあった。それは、長寿医学が正当な医療分野として認められることである。
現代医学は、あまりにも長い間、病気の予防ではなく治療ばかりに専念してきた、と同グループの専門家たちは言う。彼らは、今こそ事後対応型の保健医療から先制医療に移行するときだと考えている。それも、この分野の「ゴールドスタンダード」と医療ガイドラインを定めるという正当なやり方で進めるのだ。集まった科学者や臨床医は、自分たちが医学革命の先陣を切るのだと考えている。
この会議を主催したバック老化研究所(Buck Institute for Research on Aging)の所長であるエリック・ヴァーディンは出席者たちに「20年後、まったく新しい医学分野が始まった日としてこの会議を振り返ることになるでしょう」と語りかけた。そしてこの動きを「革命」と呼ぶのはあまりにも控えめだ、と続けた。「私たちは患者の治療のあり方に関して新たなルールを書き記すことができるのです」。
新しい医療分野を確立することは並大抵の仕事ではない。長寿を専門とする医師たちは、状況の進展に向けて、まずは学習プログラムを確立し、そのコースを医学部に組み込むことを始めている。また、この分野のガイドラインの草案を作り、各国の医師会に認められるためにどうしていくか、検討を開始した。
だが、提唱者たちは、今後直面するであろう課題を認識している。老化の評価方法や治療方法については、臨床医の間でも意見が分かれている。ほとんどのクリニックは高額で、現状では富裕層のみがターゲットだ。そして、彼らのこなすべきタスクは、現存する長寿クリニックの規模と種類の多様さゆえに、ますます難しくなっている。何しろ美容施術をする高級スパから、有効性が証明されていない幹細胞治療を施す国外のクリニックまで、多岐にわたるのだ。
基準やガイドラインがなければ、クリニックによっては顧客にサービスを提供できなくなるだけでなく、顧客に害を及ぼすかもしれないという現実的なリスクがある。
クリニック訪問
大半の長寿クリニックでは、顧客に対し、通常4~6時間をかけて複数の検査をする。血液検査はごく標準的な内容で、コレステロールや血糖値、炎症の兆しまで、臨床医があらゆることを調べる。またこれらのクリニックでは、身長と体重を測るだけでなく、身体組成、つまり体脂肪量や骨密度もチェックする。
トレッドミルに乗せられて、運動中に身体が消費できる最大酸素量である最大酸素摂取量(VO2 max)を測ることもある。認知機能、記憶力、体力を査定するところも多い。食事、生活習慣、心身の健康状態について問診をする。ほとんどのクリニックではさまざまなスキャニングもしていて、MRIスキャナーで全身を調べられたりもする。
このような初診の後、睡眠を監視するフィットネス・トラッカーやウェアラブル・デバイスを使って食生活と身体の動きを追跡し続けるクリニックもある。食事については栄養士に、メンタルヘルスについては精神分析医に、運動習慣についてはフィットネスコーチに相談することになるかもしれない。中にはゲノムやマイクロバイオームを解析するところまである。
身体がどの程度正常に機能しているのか、改善するために何ができるかを全体的に把握しようという考えだ。たとえば、VO2 maxの数値が低かったらどうだろう。HIIT(高強度インターバルトレーニング)のクラスに参加する必要があるかもしれない。自分のマイクロバイオームに重要な微生物が存在しないらしいと分かったらどうか。今後はもっと食物繊維を摂取すべきだろう。アドバイスの多くはただの常識的なものにすぎないかもしれないが、目標は、ある人の健康や生活習慣におけるどの側面が健康に長生きするのを妨げる可能性があるのかを理解し、それらに対処することである。
このような厳密な検査は、現代医学では日常的には実施されていない。コストの問題もあるが、過剰な検査は患者を不安にさせ、人を感染症の危険にさらし、誤診を増やすことにもなりかねないからだ。だが、イスラエルのラマトガンの公立病院内にあるシーバ長寿センター(Sheba Longevity Center)のエヴリン・ビショフ所長は、医師が患者の健康寿命を延ばしたいと思うなら、検査のサービスを増やす必要があると指摘する。長寿医学がメインストリームになって、加齢に伴う疾患の初期症状の発見につながるあらゆる診断検査をもっと利用しやすくする必要があるという。
ビショフ所長は、健康長寿医学協会(Healthy Longevity Medicine Society:HLMS)の開発を共同主導した。同協会は、「長寿医学の臨床的に正当な枠組みとプラットフォームを構築する」ことを主な目的として、2022年8月に設立された国際組織である。同協会は現在、医師、保健医療従事者、その他の長寿クリニック関係者など200人を超える会員を擁するとビショフ所長は言う。
ビショフ所長は、長寿医学が、たとえば心臓病学や神経学などと並ぶ医学分野として正式に認められることを望んでいる。一定の基準を満たしたクリニックが長寿クリニックとして認定されたり、資格を取得して初めて長寿の専門医を称して活動できるようになったりするのが理想だとビショフ所長は説明する。その実現のためには、米国医師会をはじめ各国の医学専門団体の承認が必要になる。
そのレベルに到達するには何年もかかることをビショフ所長は認識している。その間、まずは教育を進めるのが有効だと考えていると言う。ビショフ所長は同僚とともに、長寿医学に関心を持つ医師向けのコースを開発した。理屈のうえでは、コンピューターさえあれば誰でもこのコースを受講できるが、他と違うのは生涯医学教育認定協議会(Accreditation Council for Continuing Medical Education)の認定を受けていることだ。同コースを受講した医師は、米国における生涯医学教育をサポートする単位を取得できる。勤務先の医療機関によってはそういった生涯学習が義務付けられている場合もある。同コースはすでに4つの医学部で導入されているとビショフ所長は説明するが、現時点では未公開の情報であり、どの大学かはまだ言えないと付け加える。「これまでに6000人以上がコースを受講しました。でも、もっと増えなければなりません。理想は600万人です」。
民間の「ハイエンド」のチー長寿( Chi Longevity)クリニックを共同設立し、HLMSの会長を務める、シンガポール国立大学のアンドレア・マイヤー教授は、「長寿医学は新しい領域です」と説明する。「私たちは自らを体系化する必要があります。基準を設定しなければなりません」。
そ …
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製