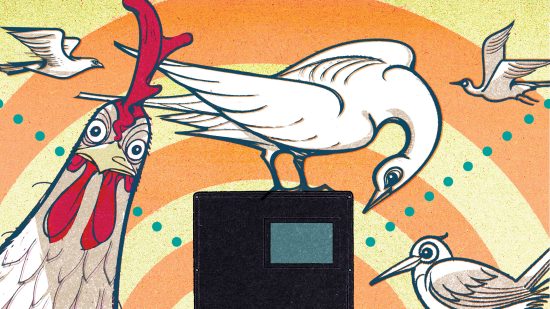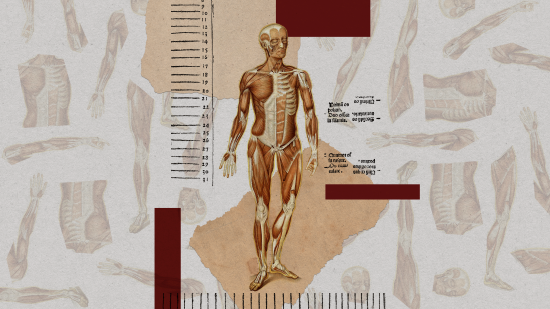見えざる生命の痕跡、
環境DNAが解き明かす
生態系の謎
環境DNA(eDNA)調査は、土、水、そして空気からでもDNAの小さな痕跡を抽出することで、科学者が生物の存在や活動を把握する方法に革命をもたらしている。その性質上、完璧な調査には向かないが、生物多様性の研究を大きく変える可能性がある。 by Peter Andrey Smith2024.08.16
- この記事の3つのポイント
-
- eDNA調査は環境中のDNA断片から生物の痕跡を探る手法である
- eDNAは希少種の発見や生態系の解明、評価に役立つ
- 精度を無視した応用など課題はあるが可能性は大きい
1980年代後半、フロリダ州ペンサコーラにある米環境保護庁(EPA)の研究施設において、タマール・バーケイ博士は泥を使って、当時の同博士にも想像できなかった革命的な手法を発見した。現在、さまざまな科学分野を揺るがしている手法の粗削りなものだった。同博士は、内陸の貯水池、汽水域の沼地、低地の塩水湿地から3つの泥サンプルを採取した。そして、それらの堆積物のサンプルを研究室のガラス瓶に入れ、水銀を加え、結果的に有毒なヘドロを作り出した。
当時、バーケイ博士は、微生物が産業汚染物質である水銀に対してどのような反応をするのかを調査していた。研究室内のペトリ皿で培養できる僅かな量の微生物を調査するだけでは不十分で、一定の範囲の環境に生息する生物すべてを理解しなければならなかった。しかし、同博士の調査の根底にあった疑問は実に普遍的なもので、今でも生物学において科学者たちを駆り立てる根本的な疑問の1つになっている。現在は研究活動から引退している同博士は先日、コロラド州ボールダーで受けたインタビューで、その疑問を次のように言い表している。「そこには、どのような生物がいるのでしょうか?」 そして、同じぐらい重要な疑問として「その生物は、そこで何をしているのでしょうか?」と付け加えた。
バーケイ博士の挙げた疑問は現在においても意義のあるもので、生態学者、公衆衛生当局、保全生物学者、法科学者、生物の進化や太古の環境の研究者らも、同じ疑問を投げかけている。また、実地調査をする疫学者や生物学者も、同博士の疑問に答えるべく、世界のどんなところへも赴いている。
1987年、『微生物学研究方法(Journal of Microbiological Methods)』誌に掲載されたバーケイ博士と同僚が執筆した論文には、ある手法の概要が記されている。その手法は、「環境DNA(eDNA:Environmental DNA)の直接抽出」と呼ばれるもので、研究者が生物の「人口調査」を実施可能にするものだった。その手法は、多少の誤りはあるが、ある環境にどのような生物が生息しているのかを知るには、実用的な手段だった。同博士はその手法を研究者としての残りのキャリアを通して使い続けた。
現在、バーケイ博士の研究はeDNA(環境DNA)の草分け的なものとして多くの研究者に参照されている。eDNAを使った調査方法は、ある環境の生物多様性や分布を比較的安価に、大規模に、時には自動化できる。例えば、単一の生物から採取したDNAを特定する従来の手法とは異なり、eDNAの収集はその生物の周囲にあるさまざまな遺伝物質も網羅する。近年では、eDNAの分野には目覚ましい進歩が見られている。「eDNAは今や、専門の科学誌があるほどです」とコペンハーゲン大学で進化遺伝学を研究するエスケ・ウィラースレヴ教授は言う。「eDNAを専門とする科学者たちのコミュニティがあります。eDNAは1つの分野として確立されているのです」。
eDNAは調査ツールとなり、一見すると見つけることが出来なさそうなものを検出するための手段を研究者に提供する。eDNAは遺伝物質、すなわち生命の設計図であるDNAの破片が入り混じったものだ。水中、土、氷床コア、綿棒、その他どのような環境でも構わず(空気中でも良い)、eDNAのサンプルを採取する。そして、採取されたeDNAのサンプルを用いれば、特定の生物を探したり、対象となる場所にどのような生物が生息しているのかを知ったりできるのである。夜の砂浜の生き物を調査する場合、eDNAを使えば、カメラを設置して砂浜に現れる生き物を観察する必要はない。eDNAならば、砂浜の足跡から生息する生き物の情報を得られるからだ。「生き物はみな、身体から小さなゴミを落としているでしょう?」とカナダのゲルフ大学に所属する生物学者のロバート・ハナー教授は話す。「細胞の小さな破片が常に剥がれ落ちているということなのです」。
ある生き物がその場所に生息することを証明する方法として、eDNAを使った手法に間違いがないというわけではない。例えば、eDNAで検知された生物は、サンプルが収集された場所には実際は生息していないかもしれない。ハナー教授は渡り鳥のアオサギを例として挙げている。アオサギがサンショウウオを捕食し、そのDNAを糞として遠く離れた場所に落とした場合だ。サンショウウオの生息が確認されたことのない場所でそのDNAが見つかるのも、渡り鳥がサンショウウオの身体の一部を遠くに運んでいるからかもしれないからだ。
それでも、eDNAは遺伝子の痕跡を解明する有効な手段になる。eDNAの中には環境の中に剥がれ落ちたものもあり、人間を含む生物の日常生活における情報を収集する、非常に興奮する、驚くような方法を提供する。
概念の基礎ができたのは、分子生物学が登場するよりも100年も前のことだ。eDNAの概念の創始者としてしばしば挙げられるのが、20世紀初頭に活躍したフランス人犯罪学者のエドモンド・ロカールだ。1929年に発表した一連の論文で、ロカールはある原理を提示した。あらゆる接触は痕跡を残す、というものだ。本質的に、eDNAとはロカールが提示した原理の21世紀版である。
eDNAの前身となる分野では(バーケイ博士の1980年代の研究も含まれる)、初期の数十年間にわたって、主に微生物の生態を解き明かすことが目的だった。eDNAという分野の進歩を振り返ってみると、eDNAはその泥から這い出て開花するまでに長い時間が必要だった。
eDNAを使った手法によって消滅した生態系を見つけ出すことができたのは、2003年になってからのことだ。ウィラースレヴ教授が主導した2003年の研究では、ティースプーン1杯分にも満たない堆積物から太古のDNAを取り出すことに成功した。eDNAを使えば、植物や体毛に覆われたマンモスなど、かつてどんな生物がそこにいたのかを知ることができる可能性があると、この研究が初めて実証した。同じ研究において、ニュージーランドの洞窟(その洞窟が凍結していなかったことは注目に値する)で採取された堆積物からは、絶滅した鳥の一種であるモアの痕跡が見つかった。このように、今ではeDNAを活用して太古のDNAの研究ができるようになった。おそらく最も驚くべきことは、eDNAを活用した数々の研究方法の元をたどれば、太古の昔に生物たちが地面に落とした莫大な量の糞から始まったということかもしれない。
ウィラースレヴ教授は、目の前にある動物の糞を眺めている時に、初めて糞の中のDNAに注目するアイデアを思い付いた。修士号を取得してから、コペンハーゲン大学で博士号を取得する前の間、研究に用いる動物の骨や骨格の残骸、その他の物理的なサンプルを得るのに苦労していた。しかし、ある年の秋に、窓の外で「犬が路上で糞をするのを眺めて」いた時だと同教授は回想する。その光景は、糞の中のDNAと、雨が降ると糞と共にDNAは跡形もなく消えてしまうことについて考えるきっかけになった。しかし、同教授はこう思った。「『そのDNAが生き残ることはあり得るのだろうか?』と考え、それを確かめる研究に取り掛かったのです」。
ウィラースレヴ教授の論文はDNAの驚くべき持続性を実証した。同教授によれば、それまでの説よりもはるかに長い時間、DNAは環境で生存できるのだという。また、同教授は、現在のグリーンランドにあるツンドラの凍土から見つかった200年前のeDNAを分析したこともある。現在は、カンボジアにある12世紀に建造されたとされる巨大な寺の遺跡群、アンコールワットから見つかったサンプルの解析に取り組んでいる。「カンボジアほどDNAの保存に向かない場所はそうはないでしょう」と同教授は言う。「なぜなら、暖かくて湿度が高いからです」。
しかし、「DNAを取り出せます」とウィラースレヴ教授は言う。
ウィラースレヴ教授だけでなく、多くの科学者がeDNAに無限の活用法を見出している。特に現在は、技術的進歩によって研究者がより多量の遺伝情報を配列決定および解析することが可能なため、eDNAにますます注目が集まっている。「eDNAは実に多くの活用法を秘めているのです」と同教授は言う。「私が思いつかないような活用法もたくさんあるでしょう」。eDNAを活用できる手法の対象は、太古のマンモスだけではない。eDNAならば、現在も生息しているものの、見つけにくい生物(の生態)も明らかにできるかもしれない。
科学者は、eDNAを用いてさまざまな形や大きさの生物を追跡する。例えば、外来種の藻の断片やネス湖のウナギ、90年近くその姿が確認されていない視力を持たない砂の中に暮らすモグラといった単一の種だ。また、野生の草の花びらに付着したeDNAや、空気中のeDNAを通じて、鳥や蜂など、どのような花粉媒介者が訪れているのかを調べることで、環境全体の生態系を知ることができる。
eDNAの歴史における次の進化的な飛躍は、地球の水環境に現在生息している生物を探す取り組みによってもたらされた。2008年、あるメディアに「水には隠れた種のDNAの記憶が保持されている」 …
- 人気の記事ランキング
-
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製