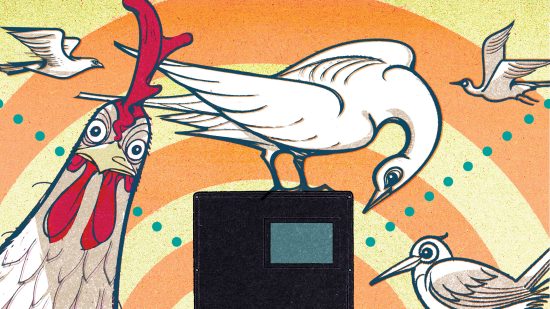人間の触覚を再現する、柔らかな電子皮膚
スタンフォード大学の研究チームは、温度と圧力を検知するセンサーを内蔵するやわらかい電子皮膚を開発した。この電子皮膚を使えば、感覚をフィードバックする、より使いやすい義肢を開発できるかもしれない。 by Rhiannon Williams2023.05.23
柔らかい電子皮膚によって、義肢を使っている人々が圧力や温度を感じ取れるようになり、身の回りのものをもっと簡単に扱えるようになるかもしれない。
実際の皮膚のように薄く引き伸ばせる電子皮膚は、絆創膏のように貼り付けることができる。外部の温度と圧力を感知するセンサーを内蔵しており、その情報を脳に埋め込まれた電極へと電気信号の形で送り込む。この信号にはさまざまな周波数があり、脳はそれを手がかりに、柔らかな感触としっかりした握手の違い、イチゴとリンゴの違い、熱さと冷たさの違いを認識する。
この人工皮膚はスタンフォード大学の研究チームが開発したものだ。同チームは、柔らかな電子皮膚の電極をラットの脳に埋め込み、自発的な動作を司る部位である運動皮質からの電気信号を記録した。ラットは刺激周波数の強さに応じ、脳が記録したさまざまなレベルの圧力に反応して脚をけいれんさせた。これは、動物やヒトが通常しているのと同じやり方で、電子皮膚がさまざまなレベルの圧力を検知できることを示している。
チームによると、この研究はより優れた義肢の実現や、人間のように知覚を感じ取るロボットの開発に役立つ可能性があるという。研究成果は2023年5月18日付けで『サイエンス』誌で論文として発表された。
「私たちの夢は、圧力、緊張、温度、振動を感知できる複数のセンサーを搭載した手全体を作ることです」と、プロジェクトに携わったスタンフォード大学の化学工学のツェナン・バオ(鲍哲南)教授は述べる。「そうすれば、本物の感覚を提供できるようになります」。
感覚的フィードバックの欠如は、人々が義肢の利用を中断する主な原因の一つになっている。利用者の不満につながるのだ。
これまでの電子皮膚でも触覚を感知する柔らかなセンサーが使われていたものがあったが、触覚を測定可能な電気信号に変換するには堅牢な外部装置に頼らざるを得なかった。こうし装置は利用者の自然な動作を妨げがちだ。今回の新しい電子皮膚は全体が柔らかく、こうした問題を回避するのに役立つ。
この電子皮膚が薄く柔らかで、ほとんど電力を使用しないという点は、義肢開発の分野に携わる人々にとって有望であると、スイス連邦工科大学の神経工学のシルベストロ・ミセラ准教授は述べる(同准教授はこのプロジェクトの関係者ではない)。
「この人工皮膚は本物の義肢に組み込まれるべきです」とミセラ准教授は言う。「明らかにそれが次の段階です」。
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製
- リアノン・ウィリアムズ [Rhiannon Williams]米国版 ニュース担当記者
- 米国版ニュースレター「ザ・ダウンロード(The Download)」の執筆を担当。MITテクノロジーレビュー入社以前は、英国「i (アイ)」紙のテクノロジー特派員、テレグラフ紙のテクノロジー担当記者を務めた。2021年には英国ジャーナリズム賞の最終選考に残ったほか、専門家としてBBCにも定期的に出演している。