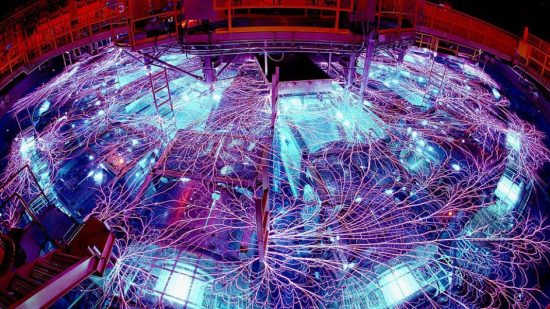MITTRが選ぶU35イノベーターはなぜ、社会課題に目を向けたのか?
MITテクノロジーレビューが選ぶ「Innovators Under 35 Japan」に選ばれた本多達也氏(富士通)、坪井俊輔氏(サグリ代表)、小嶌不二夫氏(ピリカ代表)はそれぞれ異なる立場やテーマで社会的インパクトのある課題解決に取り組んでいる。なぜ、社会課題の解決に取り組むことになったのか? 語り合った。 by Koichi Motoda2022.08.09
MITテクノロジーレビューが主催する世界的なアワードの日本版「Innovators Under 35 Japan(イノベーターズ・アンダー35ジャパン)」は8月15日まで、2022年度の候補者を募集中だ。
3年目となる「Innovators Under 35 Japan」の開催を記念し、MITテクノロジーレビューは7月22日、過去2年間の受賞者の中から本多達也氏(富士通)、坪井俊輔氏(サグリ代表)、小嶌不二夫氏(ピリカ代表)の3名をゲストに迎え、「社会課題解決」と「イノベーション」をテーマに語り合うトークセッションを東京・日本橋の「X-NIHONBASHI」で開催。オンラインで配信した。
三者三様のイノベーターたちの原点
モデレーターを務めたMITテクノロジーレビュー[日本版]の小林久編集長の最初の質問は、それぞれが課題に取り組むことになったきっかけや理由についてだった。
人工衛星データと人工知能(AI)を使った農業のデジタル化に取り組む坪井氏にとって転機となったのは、アフリカ・ルワンダ共和国での体験だった。当時、ルワンダでの教育に関わっていた坪井氏は、ほとんどの子どもたちが小学校を卒業すると農家になるという現状を知り、そうした状況を変えたいと思ったという。「実際に農業の現場を見てみると非常にアナログだったので、衛星データが活用できると思い、2018年に起業。世界にいる26億人の農家に、衛星データを活用した農業を届けていこうと考えました」(坪井氏)。
「ピリカ」というごみ拾いSNSを運営する小嶌氏は、7歳のころ、図書室で読んだ本の影響で環境問題に興味を持った。環境問題を自らの手で解決できたらおもしろいと思ったことが現在の活動の原点になったという。大学進学後は研究者の道を目指したが、大学院の研究室もインターン先の企業も自分には向いていないと感じ、起業を考えるようになった。「まだ誰も手を付けていない大きな社会課題を見つけたいと思って世界中を旅しました。そして、ごみのポイ捨て問題が世界各国で悪化していることを目の当たりにし、興味を持ちました」(小嶌氏)。
富士通で「Ontenna(オンテナ)」を開発した本多氏は、大学1年生の時に聴覚障害者と出会った。手話に興味を持ち、勉強して手話通訳のボランティアをしたりと、ろう者に関わり始めた。「大学ではデザインやテクノロジーの勉強をしてたので、そういったものを使って彼らに音を伝えたいという思いで開発したのが、音を光と振動で感じるOntennaというデバイスです」(本多氏)。
個人の体験が起点となって社会課題の解決に取り組んでいるイノベーターたちの話を聞いた小林編集長は、「社会課題解決に取り組むのは政府や大企業というイメージが一般にあると思います。そういった組織に対して思うことはありますか?」と尋ねた。
坪井氏は、最初のうちは社会課題は政府や大企業が取り組みべきものだと思っていたが、起業によって意識が変わっていったという。「何ごとにおいても自分ごとであり、自分が解決しなければという使命感に変わってきます。人生最後の時に、これをやったことでありがとうと言ってもらいたい、と思うようになりました」(坪井氏)。
本多氏の場合は、大学院時代の研究を富士通入社後も続けることで、Ontennaの製品化に漕ぎ着けた。ハードウェアの製品化に関しては、やはり大学だけでは難しかったという。「学生時代にIPA(情報処理推進機構)の未踏IT人材発掘・育成事業のプロジェクトに採択されたことがきっかけとなり、富士通の方を紹介してもらって入社することができました。一からプロジェクトを立ち上げて予算も付けてくれるという、理解あるトップが大企業にもいます」(本多氏)。
小嶌氏は、尊敬するユーグレナの創業者・出雲 充氏が語ったという、「500社営業したら500社目に協力者が現れた」という話を信じて営業してみたら、「100社目くらいで協力者が現れたのでラッキーだった」という経験を語った。
ここで小林編集長は坪井氏の話を振り返り、「宇宙とルワンダの子どたちという、本来ならあまり繋がらない接点を見つけることで新しい課題や事業に気づいた。そういう気づきには偶然性が大事なのか、それとも自分を突き詰めるとやりたいことが見えてくるのか」と質問。それに対し坪井氏は、「やりたいことが分からない場合は、自分の居場所だと思っている領域から少し外れてみるべき」と答えた。「ルワンダは人口の半数が農家なので、日本にいたら想像もつかない状況が起きています。そういうところに行くと、感じるものが違います」(坪井氏)。

課題解決の取り組みを広げていくのに必要なこと
話題は、それぞれの活動をより社会全体に波及させていくために必要な視点や考え方について移っていく。
本多氏が重視しているのは、取り組みを知ってもらうきっかけを積極的に作ることだという。例えばOntennaを使った音楽イベントでは、耳が聞こえる人にも付けてもらって臨場感や一体感を感じてもらう。そうやって障害のことを学んでもらう、きっかけ作りを大切にしているという。「今後は、どうやって社会課題とのタッチポイントをデザインしていくかが重要になってくると思います。スポーツ鑑賞でも、卓球台の下に置いたマイクから伝わってくるピンポン球のリズムを感じるとか、視覚聴覚以外の感覚を使った体験はだれにとっても楽しいものです」(本多氏)。
一方、坪井氏は「自分自身をきちんと持っていること」だと話す。新しいテクノロジーに挑戦するのはよいことだが、それに飲み込まれてしまうのはもったいないと感じている。「今の自分の取り組みは衛星データ使っているので、宇宙ベンチャーのカテゴリーで紹介されることもありますが、目的はあくまで社会課題の解決なので違和感を覚えることもあります。自分自身をきちんと持っていることが重要だと思います」(坪井氏)。
小嶌氏は、映画『アポロ13』の中で、宇宙船内で二酸化炭素を吸着する装置が壊れてしまった時に、地上にいるエンジニアたちが会議室に集められ、宇宙船の中にあるものだけを使って解決策を見つ出すシーンが好きだという。「見てくれが悪かったり最先端ではないけれど、制約条件がある中で問題を解決することがかっこいい」。
こうしたやりとりを受けて、小林編集長は「まず動くことが大事。周りと摩擦が起きようとも、自分が正しいと思うことや、やってみたいことに取り組んでいくことで見えてくるものがあるということですね」と感想を述べた。
これからイノベーターを目指す人に向けて
トークセッションの最後は、本年度の候補者募集に関連して、同世代や後進の人たちへの期待を聞いた。
本多氏は、「今でも自分はもがいている」と言う。「MITテクノロジーレビューのInnovators Under 35はそういう人たちに、大丈夫だよ、もっと頑張れと言ってくれる。今やりたいことがある人は、それを信じてチャレンジすることが、認めてもらうきっかけになると思います」(本多氏)。
「自分は凡人」だと話す坪井氏は、「実際に私は2回目の挑戦でInnovators Under 35を受賞しました。大学生の時に革新的な技術を持っていたわけでもなく、平凡な大学生がいろいろと旅をしながら自分の道を決めた」と語る。「その当時、ソフトバンクの孫正義氏が『若いうちに高い志を持たなかったらあっという間に人生が終わってしまう』と言っていた言葉がずっと残っている。もがいて焦りながら見つけた最適解が自分の道になってくると思います」(坪井氏)。
小嶌氏はタレントの木村拓哉さんの「自分ではなく親戚が勝手に履歴書を送った」というエピソードが、「かっこいいと思う」と紹介した。「自分も他薦してもらいたかったが、自薦するしかなかった。自薦でもチャレンジして欲しいし、周りの方もぜひ積極的に有望な方を推薦してほしいですね」(小嶌氏)。

MITテクノロジーレビューは[日本版]は、才能ある若きイノベーターたちを讃え、その活動を支援することを目的とした「Innovators Under 35 Japan」の候補者を募集中。詳しくは公式サイトをご覧ください。
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製
- 元田光一 [Koichi Motoda]日本版 ライター
- サイエンスライター。日本ソフトバンク(現ソフトバンク)でソフトウェアのマニュアル制作に携わった後、理工学系出版社オーム社にて書籍の編集、月刊誌の取材・執筆の経験を積む。現在、ICTからエレクトロニクス、AI、ロボット、地球環境、素粒子物理学まで、幅広い分野で「難しい専門知識をだれでもが理解できるように解説するエキスパート」として活躍。