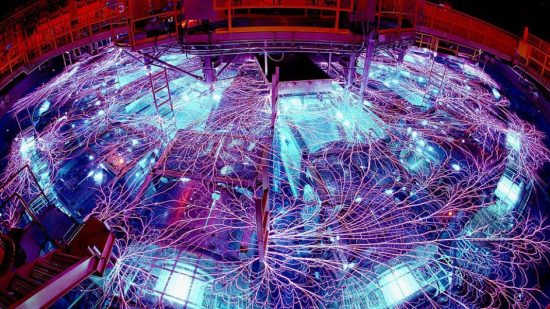ボディシェアリング提唱者・玉城絵美が考えるイノベーターの条件
重さや位置の感覚といった固有感覚の共有により、能動的かつ臨場感のある体験共有を可能にする「ボディシェアリング」。大学での研究教育活動に取り組みながら、ベンチャー企業の創業者として事業化も進める玉城絵美・琉球大学工学部教授に、同技術の現在地と将来像、そしてイノベーターの条件について聞いた。 by Noriko Higo2022.07.26
MITテクノロジーレビューが主催する世界的なアワードの日本版「Innovators Under 35 Japan(イノベーターズ・アンダー35ジャパン)」が、本年も開催される。8月15日まで、公式サイトで候補者の推薦および応募を受付中だ。
本年度の審査員の1人である玉城絵美氏は、手の動作を制御する装置「PossessedHand(ポゼストハンド)」を開発し、人工知能(AI)、ヒューマン・コンピューター・インタラクション(HCI)の分野で研究を進める傍ら、28歳でH2L,Inc.を起業。2021年には琉球大学工学部で女性初となる教授に就任し、現在はNTTドコモなどとの協業や、映画「竜とそばかすの姫」の技術アドバイザーなども務めている。世界的な注目を浴びた発明によって新分野を切り開いてきた玉城教授は、研究や事業をどのように進めているのか。話を聞いた。
◆◆◆
重さや位置といった固有感覚の伝達により、体験を共有する
──玉城先生が取り組まれている「ボディシェアリング」とはどのような研究でしょうか。
H2L, Inc. CEO、琉球大学工学部教授
人間とコンピュータの間の情報交換を促進することによって、豊かな身体経験を共有するBodySharingとヒューマンコンピュータインタラクション研究とその普及を目指す研究者兼起業家。2011年に手の動作を制御する装置PossessedHandを発表しTime誌が選ぶ50の発明に選出。2012年にH2L,Inc.を創業し、UnlimitedHand, FirstVRなどの製品を発表しサービスへと展開。2020年国際会議AugmentedHumanにて、近年で最も推奨される研究論文として表彰。近著に『BODY SHARING 身体の制約なき未来』(大和書房)がある。
「ボディシェアリング」は、人の体やロボット、アバターなどと、ユーザー側のさまざまな身体感覚を共有して、「体験」を共有するための技術です。これまでの視覚や聴覚だけではなく、もっと能動的で臨場感のある体験共有のために必要な「固有感覚」の共有について研究しています。
固有感覚の例としては、りんごが手の上に乗っているという重量覚、手を握ろうとしてもりんごがあるので握り込めないという抵抗覚、また、りんごを取るために手指を伸ばしているという位置覚などが挙げられます。
例えばカヤックに乗るという体験の場合、一般的な視覚や聴覚に加えて、水の重さやどのようにパドルを漕ぐかといった固有感覚まで共有できます。その結果、ユーザーの没入感や臨場感に関する身体所有感は、固有感覚を提示しないときと比べて、36.0〜53.5%向上します。
また、筋肉に対する光の反射量を検出する筋変位センサーを用いて筋変位データを取得することで、力の入れ具合をスマートフォンに表示させる、すなわち、「見える化」することも可能です。今まで見ることができなった感覚を数値化できれば、一見同じに見えるプロスポーツ選手とアマチュア選手の動作でも、力の入れ具合が全然違っていることがわかり、感覚を定量的に伝えることができるようになります。
研究成果の事業化も積極的に進めています。具体的には、スマートフォンで遠隔地のロボットを操作してイチゴを収穫する遠隔農業や、部屋の中にいながら観光している感覚を楽しめる遠隔観光が可能です。また、デバイスを腕に装着するだけで、運動中の動きをスポーツトレーナーと比較できるエクササイズアプリも開発しました。さまざまな理由で外出困難な方が、部屋の中で体験できる機会を徐々に提供できるようになってきました。
さらに、これまでは視覚化できなかった「緊張」や「残体力」の情報を筋変位データから推定し、メタバース空間のアバターに反映するシステムも開発しています。リモートワーカーの「緊張」や「残体力」の情報をメタバース空間に反映することで、コミュニケーションが円滑に取れるようになります。
──VR(バーチャル・リアリティ、実質現実)など近い分野の研究も盛んですが、他の研究との違い、特徴はどこにありますか?
確かにVRやロボットを手がけるスタートアップは多いですが、実は固有感覚の伝達ハードウェアから作っているのはほぼ私たちだけです。
固有感覚の伝達ができて、その後どうロボットや人間を制御するのか、どのように体験を共有するのかという研究はされています。しかし、実際にセンサーやアクチュエータ、つまり人間やロボットなどからデータを取得してそれを動作に変えるデバイスを開発しているところは今もほとんどありません。でも、だからこそ、この研究を立ち上げた意味があるし、多くの方々に使っていただいています。
体験を共有することで、どんな人の人生も豊かにしたい
──「ボディシェアリング」の研究が目指すゴールを教えてください。
部屋の中にいても、外に出かけて楽しむ以上のたくさんの体験を共有できることを、最終的な研究のゴールとしています。
例えば、1日休みがあって、陶芸がしたい、スポーツもしたい、どこかで観光もしたいと思ったとします。物理的に1日では回れませんが、ボディシェアリングを利用すればそれが可能になります。
陶芸の粘土をこねるのはショートカットして、成形だけする。観光地に行くまでの行程はカットして目的地の景観だけ楽しむ。あるいは逆に、観光地への行き帰りが好きな人はそれを楽しむ。そんなふうに好きな体験だけを抽出・合成して、1日でいっきに本人が希望する体験を得るところまでできるようにするのが、研究としての最終形態だと考えています。

これを私たちは、ボディシェアリングによって実現する「マルチスレッド・ライフスタイル(並列的な生)」と名付けています。ボディシェアリングによって、体験の制約をなくし、体験を共有することによって、人間の人生を豊かにしたいですね。
──いつ頃の実現を目指していますか?
2029年を予定しています。ボディシェアリングの研究は2006年からスタートしていますが、比較的早い段階で2029年までの計画をすべて立てました。少し先に進み過ぎたり、逆になかなかうまくいかなかったりして、1、2年の前後はありますが、今の時点では計画どおりに進んでいます。
医療への応用も進めていて、最近発表したのが、脊椎損傷患者のリハビリ機器の共同開発です。伊藤超短波とH2L, Inc.が、東京都中小企業振興公社の助成を受け、脊髄損傷をはじめとする神経障害による麻痺患者向けに、手指動作に関するリハビリテーション機器を発表しました。
研究では、手指の拘縮のある患者に、筋肉に電気刺激を与えて指を動かすことのできる「PossessedHand(ポゼストハンド)」という機器を装着してもらい、手の動作を教示してリハビリしてもらいました。通常のリハビリでは治療できなかった方ですが、電気刺激による動作教示を1年間続けたところ、筋力が戻り簡単なものなら持つことができるようになりました。2015年から続けてきた研究で、2022年になってやっと発表に漕ぎつけました。
これらの研究は、筋肉の膨らみ(筋変位)から手の動作や力の入れ具合などの固有感覚を検出するセンサー技術と、多電極の電気刺激を腕に与えて手指の動作をはじめとする固有感覚を伝えるアクチュエーション技術を用いており、この応用を進めています。

科学の成果を社会につなぐには、他分野との連携が重要
──現在、関心を持っている社会的な課題はありますか?
さまざまなところで、研究成果を社会にうまく引き継げていないことですね。研究成果を産業化する、いわゆるイノベーション・エコノミーを作るのが現状は難しいと感じています。具体的な例を挙げると、VRゴーグルやマウントヘッドディスプレイが当てはまるかもしれません。
数年前にVRゴーグルが社会に出始めた頃、本来なら政府なり企業なりが出すべきだった「安全ガイドライン」が存在していませんでした。そのため、「何歳まで付けていいの?」「斜視になるリスクがあるのでは?」といった不安や誤解がそのままになってしまい、それがVRゴーグルなどの産業化を妨げる要因になったのではないかと考えています。
VRゴーグルはあくまで一例ですが、安全ガイドラインを適切なタイミングで出して、不安や疑問をクリアできていれば、もっと世の中にスケールできたのではないかと思います。こうしたケースは少なくありません。
──こうした課題について、どのような解決策が考えられますか?
各研究分野がきちんと連携することですね。工学系の研究なら安全工学分野とつながる、文系で法規制を研究している方たちともつながる、また標準化について研究している方々と連携するなどです。各分野との連携が取れていれば、突然VRゴーグルが完成して法律も標準化も間に合わないといったことは起きず、「そろそろこの技術・製品が世に出るから、法律に関しての研究も進めてください」となっていくはずです。
ちなみに、私たちの研究グループでは法整備の方々との連携に加えて、自分たちでも法律のエビデンスになるような研究をしています。ボディシェアリングは没入感が非常に強いので、例えばその場にいる10人が全員ボディシェアリングで「ハワイにいる」状態だと、すぐ近くで犯罪が起きていても身体感覚ではハワイにいるのでわからない。危機回避能力が低くなります。
ただ、それでは社会で使うことはできません。そこで、どの程度なら安心・安全に使えるのかをシミュレーションして、その結果を経済学や生態学の分野の方々と連携しながら、安全に使うための時間など規制についてエビデンスを出すようにしています。
20代での起業で、事業化を意識しつつ研究を進められた
──玉城先生には「Innovators Under 35 Japan」の審査員をお願いしていますが、先生ご自身の「Under 35」について教えてください。
実は、私はまさに35歳で起業しようと考えていました。研究計画の上では、技術の成熟度が事業化に足り得るレベルに達するのが35歳だったからです。でも、20代の頃に周囲に起業する人が多く、ついうっかりつられて28歳で起業することになりました(笑)。
技術的には未成熟なレベルで起業したわけですが、結果的には良かったと思っています。起業したことで、事業フェーズを意識しながら研究を進めていくことができました。また、自分の研究成果をいち早くユーザーの方々に届けることができたのも、早い段階で起業したからだと考えています。
今は、筋変位センサーを使用していますが、2012年頃は筋肉の神経信号を増幅して、そこからデータを取る筋電をセンサーにしようと考えていました。
筋電を使うことは一般的でしたし、私と研究チームも少なくとも1年は筋電で手指の固有感覚センサーデータを取ろうと研究しました。ただ、実際に研究を始めてみたら、データにノイズが乗ってしまって使い物になりませんでした。
例えば、スマートフォンを手に持っていたら、筋肉の電気信号よりスマートフォンの信号のほうが大きいので、そちらを拾ってしまいます。蛍光灯の振幅ノイズや充電器のアダプタのノイズも同様です。何も手に持たないリハビリの現場では使えても、日常生活でスマートフォンやパソコンを使わないことは考えられません。一生懸命ノイズを除去し続けましたが、1年以上かけても事業化どころか論文の1本も書けない時期がありました。
時間はかかるけれど新たにセンサーを作り直して、筋変位に変えたことで、計画どおり2029年の研究ゴールに向けて進められるようになりました。あと、この挫折の経験で精神的に強くなりましたね。何かあっても寝ればどうにかなる、みたいな(笑)。
──最後に、玉城先生が考える「イノベーター」の条件を教えてください。
何事にもディスラプティブ(破壊的)であることだと思います。モノ作りをしている人だけ、新しいサービスを開発している人だけがイノベーターではありません。
何かを生み出すことは破壊的です。きちんと自立していて、世の中に新しい価値を提供できる人は、どんな方もイノベーターだと私は思います。「自分はイノベーターと言えるようなことはしていない」と思わずに、ぜひ胸を張ってイノベーターとして世の中に出て来てほしいですね。

MITテクノロジーレビューは[日本版]は、才能ある若きイノベーターたちを讃え、その活動を支援することを目的とした「Innovators Under 35 Japan」の候補者を募集中。詳しくは公式サイトをご覧ください。
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製
- 肥後紀子 [Noriko Higo]日本版 フリーランスライター
- ライター・編集者