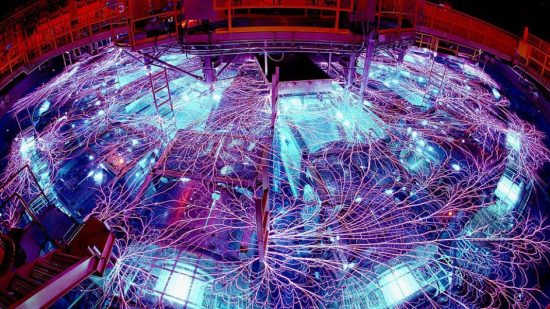森川博之教授:
「草の根」から始まる新しいスマートシティ論
スマートシティといえば、「最新テクノロジーを積極的に取り入れて、人々の生活をより豊かなものにする」といったイメージが強い。しかし、東京大学の森川博之教授は「その発想は変えたほうがいい」と警鐘を鳴らす。第一人者が語るスマートシティの現状、問題点、そして未来とは。 by MIT Technology Review Japan2021.11.15
交通量に応じて動く交通機関、無人シャトルバス、廃棄物収集ロボット、環境に優しいクリーンエネルギーの創出、最新技術による手頃な価格の住宅提供、それに伴う人口の増加。ひいては雇用創出・経済活性化......これがグーグルが目指した“未来都市”だった。2017年10月、グーグルの親会社であるアルファベット傘下のサイドウォーク・ラボ(Sidewalk Labs)が、カナダ・トロントのウォーターフロント・エリアをスマートシティとして再開発するプロジェクトを発表。街中に大量のセンサーを張り巡らし、ビッグデータに基づいて自動制御されるという、本格的かつ大規模なスマートシティ計画は、当時大きな話題となった。ところがサイドウォーク・ラボは2020年5月、コロナ禍で先行きが不透明になったなどとして計画からの撤退を発表した。また、スマートシティの先進事例として、さまざまな企業が参入し、盛り上がりを見せていたスペイン・バルセロナのプロジェクトも、近年は熱が冷めつつあるようだ。

- この記事はマガジン「Cities Issue」に収録されています。 マガジンの紹介
SF世界さながらの便利な暮らしだけでなく、交通渋滞や公害、廃棄物、自然との調和など都市が抱える課題を解決し得るはずのスマートシティだが、現在の潮流を見ると、当初の期待どおりには進んでいないように見える。それはなぜか。
そもそもスマートシティが注目されるようになったのは、「センサー」「無線通信」「クラウド」という、3つのカギとなるテクノロジーがこの10年で目覚ましい進化を遂げたからだ、と話すのは、東京大学工学部の森川博之教授。森川教授は、政府や自治体の政策提言にも関わり、日本におけるIoT(モノのインターネット)の第一人者として知られている。
「これら3つがここ10年間で整ってきたことで、スマートシティの開発が推進されるようになってきました。センサーでリアルなデータを収集し、そのデータを無線通信で送信してクラウドで集められるようになった、ということです」
森川教授は、スマートシティがこうした「技術偏重で進んできた」ことを認めつつ、現状について「従来と変わりなく夢を抱く捉え方と、冷静になって見つめている捉え方の2つがせめぎあっている状態」と表現する。
「これまでのスマートシティ・プロジェクトがうまくいっていない理由は単純で、お金が流れていないからです。だから企業としてもそこまで投資はできない。とはいえ、一般にスマートシティと呼ばれているものがカバーする範囲は幅広く、我々の生活を取り巻くすべてが対象になり得ます。ですから、スマートシティが目指していることは、我々が今後もずっと考えていかねばならないことではあります」
森川教授は、スマート・モビリティ、スマート・エコノミー、スマート・ガバメント、スマート・エンバイロメントなどの具体的な構成要素を挙げ、「スマートシティの概念が今後も続くのは間違いない」と話す。
「ただ、それに向けて急に盛り上がったとしても、持続的にならないのは、繰り返しになりますが、お金が流れていないから。そこが最も大きな問題です。“お金”とは“価値”のこと。そこで生活している人に価値を提供することさえできれば、生活者もそれに対してお金を使ってもいいと考えるはずです。ところが現状では提供される価値が投資に対して見合っていない。スマートシティをうまく持続させるには、対価を払ってもいいと思える“価値”を、地道に1つ1つ作っていくしかありません」
価値を生むカギは「多様性」と「気づき」
スマートシティの“価値”を生み出すにはどうしたらいいのだろうか。森川教授はスマートシティの特徴を「データですべてがつながるデジタル化」と「扱う範囲の幅広さ」とした上で、それらを踏まえた「これまでのビジネスとは異なる進め方や仕組みで価値を生む必要がある」と話す。
「デジタル化とは、データですべてがつながっていくということです。サプライチェーンを例に挙げると、流通の上流から下流までがデータでつながっていく。今までのビジネスであれば、上流から下流の間の“ある部分”だけを見て当事者はビジネス展開すればよかったのが、デジタル化したビジネスモデルでは上流から下流まですべてを見渡す必要があります。これがデジタル時代の特徴であり、まさにスマートシティそのものと言えるでしょう。
また、スマートシティが扱う範囲は広く、自治体、不動産、ICT業界など膨大なステークホルダーの利害が関係してきます。関わる人やモノが一気に増え、そうした人たちを巻き込んで、一緒に作り上げていかなければなりません。それにはさまざまな人たちが、お互いに敬いながら受け入れ合っていくことが大切です」
都市にはさまざまな年齢や性別、出身、収入などの属性を持つ多様な人たちが集まり住んでいる。にもかかわらず、「日本でスマートシティの議論をしているのは、私たちのようなス …
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製