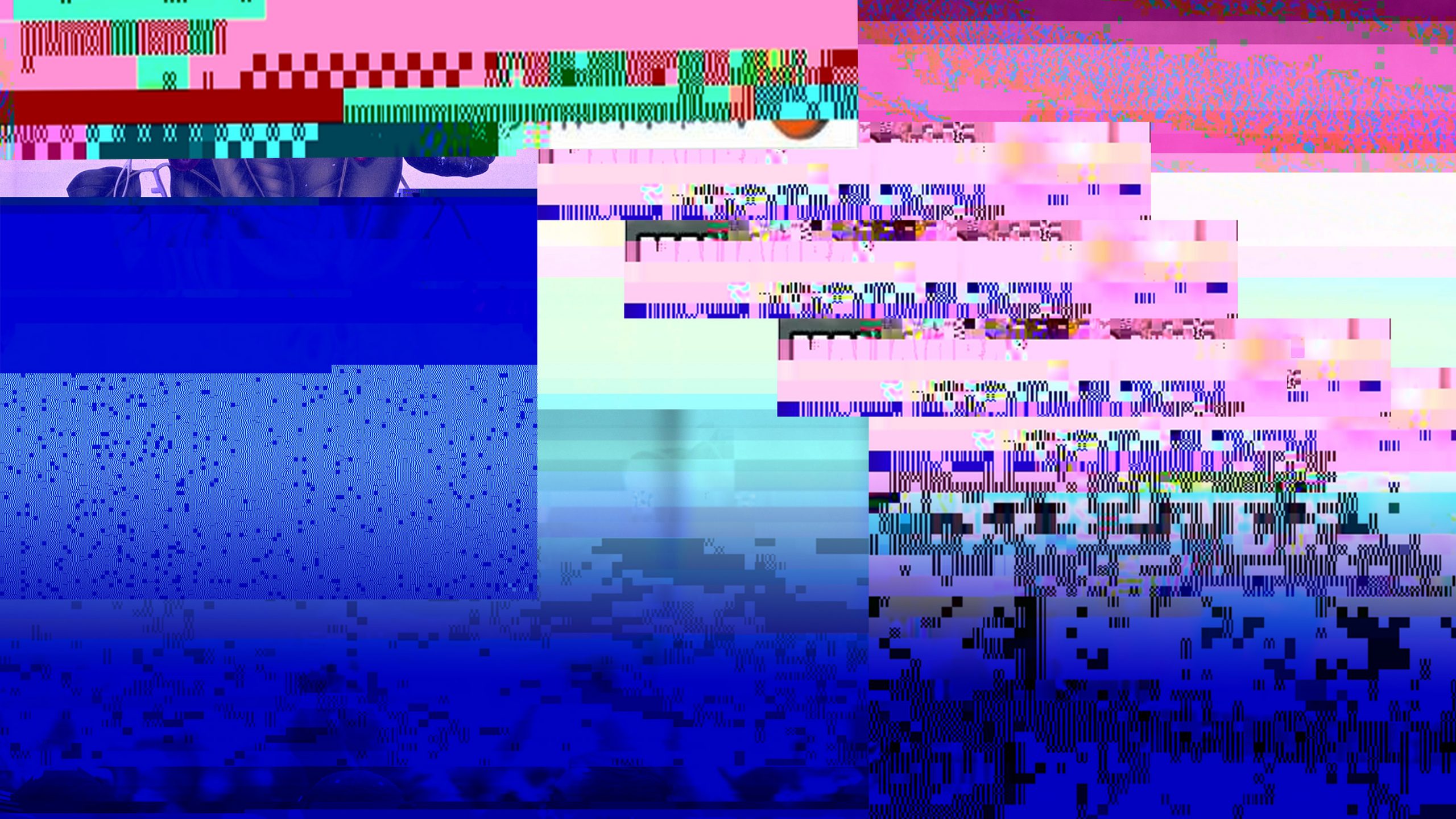国家による「ネット遮断」の問題点、グーグル・ジグソー責任者に聞く
グーグルのジグソー・プロジェクトの報告書によると、最近になって各国政府は指数関数的なペースでインターネットを遮断しているという。同プロジェクトの責任者が、インターネット遮断がなぜ問題なのか、どう取り組むべきなのか語った。 by Tate Ryan-Mosley2021.09.24
最近の報告によると、世界中で政府が意図的にインターネットを遮断しており、その頻度や巧妙さは増している。グーグルの「ジグソー(Jigsaw)」プロジェクトが、デジタル権利を擁護する非営利団体「アクセス・ナウ(Access Now)」、検閲を監視する企業「センサード・プラネット(Censored Planet)」とともに公表した調査報告によると、インターネットの遮断は「指数関数的」に増加しており、過去10年間に確認された約850件のネット遮断のうち、768件が2016年以降に発生したものだった。
インド政府は他のどの国よりも頻繁にインターネットを遮断しており、その回数は2020年だけで109回にも上る。データを見ると、ネットの遮断は選挙や内乱が起こりそうな時期に多く発生しており、反対派を抑え込むための戦術になっていると言われている。そうした流れが加速する一方、遮断は巧妙化しており、URLへのアクセスを大幅に遅延させるスロットリングや、特定のインターネットアドレスのブロック、モバイルデータの使用制限などの方策がとられている。
MITテクノロジーレビューは、拡大し続けるインターネット遮断について、ジグソー・プロジェクトのダン・カイザーリング最高執行責任者(COO)に話を聞いた。
なお、以下のインタビューは、発言の趣旨を明確にし、長さを調整するため、編集されている。
◆
——この研究プロジェクトはどこから生まれたのですか?
設立当初から、ジグソーとその前身である「グーグル・アイデア(Google Ideas)」は、オンライン検閲や、世界各国の政府が情報へのアクセスを制限しようとする取り組みについて研究してきました。何が起こっているのかを知ることは最初の、そして最も重要なステップのひとつです。
特に軽度の検閲だと、体験者にも何が起こっているのかをはっきりと把握できるとは限りません。例えば、特定のインターネットサイトへの接続を著しく遅らせて使えなくするスロットリングは、ユーザーの側からすると、技術的な問題のように見えることもあります。
問題が悪化しているため、私たちはすぐにこの報告書を公表したいと考えました。インターネットの遮断は、以前より頻繁に実施されています。市民の行動に影響を与える手段として、インターネットアクセスの制限を実験的に試みる政府が増えています。
インターネット遮断のコストが増加していることはほぼ確実です。それは、政府のアプローチ方法が緻密化していること、そして、人々が生活の中でより多くの時間をオンラインで過ごすようになっていることに起因しています。
そこで私たちは、インターネットの遮断に反対する国際的な合意を得るため、行動を呼びかけたいと考えました。最近、国連をはじめとする政府間組織が、インターネットの遮断を人権侵害だと非難する声明を出したことに後押しされました。6月に国連特別報告者が極めて率直な内容の声明を出し、この問題がどれほど深刻化していて、なぜすべての加盟国への脅威となっているのかを説明しました。
——技術的、また社会的視点から見た場合のインターネット遮断とはどのようなものですか?
「インターネット遮断(Internet shutdown)」とは、情報へのアクセスを制限する活動のことです。この言葉はインターネットの完全な遮断を指すと考えている人が多いと思います。確かにそれも実際に起こっていて、特にこの数年、特定の国々で多く見られています。 しかし、より軽微でありながら、ある意味ではインターネットが完全に遮断されるのと同程度のダメージを与える、さまざまな脅威があります。インターネットの完全遮断に反対する国際的な同意が強まるにつれ、より巧妙で、ターゲットを絞った軽度の遮断や検閲が増加しています。
——こうした遮断について理解するうえで、技術面で障害となるものは何ですか?
昔から言われているように、測定できないものは管理できません。基本的には、何かが妨害されたことを …
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製