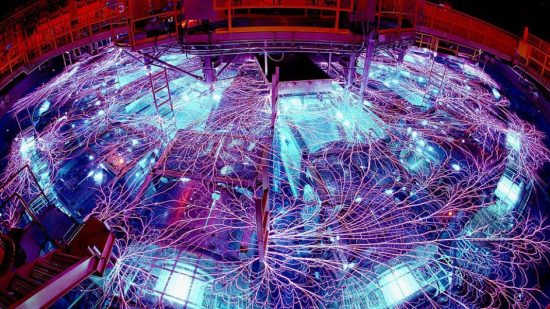インド政府がアドハー・プロジェクトを導入した2009年、アンバ・カックはインドのロースクールに通っていた。インドの包括的なIDプログラムとして構想されたこの生体認証IDシステムは、あらゆる居住者の指紋や虹彩スキャン、写真を収集しようとしていた。それが悲惨な事態を招いているという話が広がるのにそう時間はかからなかったと、カックは回想する。「手を使う仕事をする肉体労働者の指紋がシステムに登録されず、基本的生活必需品を手に入れられなくなっているという報告を突然耳にするようになりました」とカックは言う。「生体認証システムが引き起こした障害による餓死者が、インドでは実際に出たのです。だからこそ、真に重要な問題でした」(カック)。
こういった事実をきっかけに、カックは生体認証システムとその責任を問う法律を研究するようになった。今やニューヨークに本拠を置くAIナウ研究所のグローバル戦略プログラム部長を務めるカックは、2020年9月2日、世界各地の生体認証システム規制について、8つのケーススタディを詳細にまとめた報告書を発表した。内容は、市や州、国、そして世界的な取り組みにわたり、非営利団体に関するものも含む。その目的は、機能するアプローチと失敗するアプローチについての理解を深めることにある。学んだ点や、今後進むべき方向について、カックに話を聞いた。
※以下のインタビューは、発言の趣旨を明確にするため、要約・編集されている。
◆◆◆
——このプロジェクトのきっかけは何だったのでしょうか?
生体認証技術は、政府の領域だけでなく、私たちの生活においても増殖し常態化しつつあります。顔認識を用いた抗議活動の監視は、2020年だけでも香港やデリー、デトロイト、ボルチモアで実施されました。あまり知られていませんが、福祉サービスを受けるための条件として生体認証を利用する生体認証IDシステムも、アジアやアフリカ、ラテンアメリカの低・中所得国で普及しています。
しかし興味深いのは、生体認証システムに対する反発がピークに達していることです。生体認証システムの擁護派は、これまでにないほど注目を浴びています。そこで問題となるのは、法律や政策がどう関わるかということです。そこで、この報告書が登場するわけです。ここでは、政府や支援団体が規制強化を強く求める姿勢を見せた場合に、これらの経験から学べることを引き出そうとしています。
——世界的な生体認証規制の現状はどうなっているのでしょうか? このエマージングテクノロジーを扱う法的枠組みはどのくらい熟慮されているのでしょうか?
世界にはデータ保護法を制定している国が約130カ国あります。ほとんどすべての国で生体情報を対象としています。つまり、生体情報を規制する法律があるのかという問われれば、ほとんどの国に存在するというのが答えです。
しかし、もう少し掘り下げると、データ保護法の限界とは何でしょうか。データ保護法では、生体情報が使用された場合に規制し、同意を得なければ使用できないようにするので精一杯です。しかし、精度や差別などの問題は、法的にはまだほとんど注目されていません。
一方で、このテクノロジーを完全に禁止するというのはどうでしょうか。米国では市や州レベルで集中的に活用されています。こういった政府活動のほとんどは、公共の、さらに特定すれば警察による使用に集中していることを、忘れがちだと思います。
そして、セーフガードが用意されているデータ保護法はさまざまありますが、その効力は本質的には制限されています。また、米国の地方都市や州レベルでは、生体情報の使用を禁止する地域もあります。
——ケーススタディから見えてきた共通テーマは何でしょうか?
私にとって最も明解だったのは、ナヤンタラ・ランガナサン(弁護士/独立研究者)によるインドの章と、モニーク・マン博士(メルボルン法科大学院)とジェイク・ゴールデンフィン博士(ディーキン大学)によるオーストラリアの顔認識データベースの章です。いずれも大規模な中央集権国家型アーキテクチャーで、異なる州や別の種類のデータベース間で技術的な連携のない状態のデータを取り除いたうえで、これらのデータベースが中央で結びつくようにしています。つまり、中央で結びつく中央集権型の巨大な生体情報アーキテクチャーを構築しているわけです。そして、この重大な問題の解決策として、「データ保護法のおかげで、まったく想定されない目的にはデータが決して使われることはない」と言いたいのでしょう。し …
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製