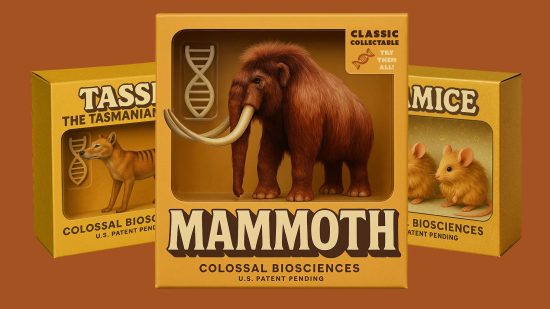ガーディアン(Guardian )紙は5月29日、グーグル・アシスタント開発の実態をレポートした記事を掲載した。26の言語を理解するグーグル・アシスタントの「魔法」のような能力の背後には、下請け業者として働き、グーグル・アシスタントが機能するように膨大な量の学習データをひたすらラベル付けする大勢のマルチリンガルたちのチームが存在する。彼らは低賃金で働き、日常的にサービス残業を強いられている。労働条件に対する要求は、繰り返し退けられてきた。
これは、人工知能(AI)業界の運営実態を暴き始めた数十の話の中の1つに過ぎない。人間の労働者は、AIを機能させるためにデータにラベル付けをするだけではない。時には人間の労働者がAIの役割を果たす。フェイスブックのコンテンツを監視するAIの背後には、何千人ものコンテンツモデレーターが存在する。アマゾン・アレクサの背後には、文字起こしのグローバルチームが存在する。そしてグーグル・デュープレックス(Duplex)の背後では、人間を真似るAIを模倣する人間が電話をかけていることもある。AIを機能させるのは魔法の杖ではない。自分たちの作業を自動化できるまで、徹底的にアルゴリズムを訓練する見えざる労働者の力で動いている。
書籍『Ghost Work: How to Stop Silicon Valley from Building a New Global Underclass(ゴーストワーク:シリコンバレーが全世界に新たな貧困層を作り出すのを止める方法)』を5月に出版したばかりの人類学者のメアリー・グレイとコンピューター科学者のシッダールタ・スリは、今後誰もがその見えざる労働者になる可能性があると訴える。
人々はなぜゴーストワークをしようとするのか? 社会から見えにくい労働形態がどのように劣悪な労働環境を導くのか? どうすればこの新たな労働形態をより持続可能なものにできるのか? メアリー・グレイに話を聞いた。
#
——「ゴーストワーク」の定義を教えてください。
ゴーストワークとは、部分的にでもアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)とインターネットを利用し、調達、スケジュール、管理、出荷、および開発ができるような仕事のことです。少しAIを利用することもあります。人間が関与しておらず、ソフトウェアが魔法のように稼働しているだけとされる仕事は、ほぼ間違いなくゴーストワークです。
——ということは、最終製品またはサービスがどのように販売されているかに左右されるということですか。
そうです。仕事や成果そのものは、本質的には良いものでも悪いものでもありません。それを良くも悪くもするのは、具体的に言えば労働条件で …
- 人気の記事ランキング
-
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製
- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏