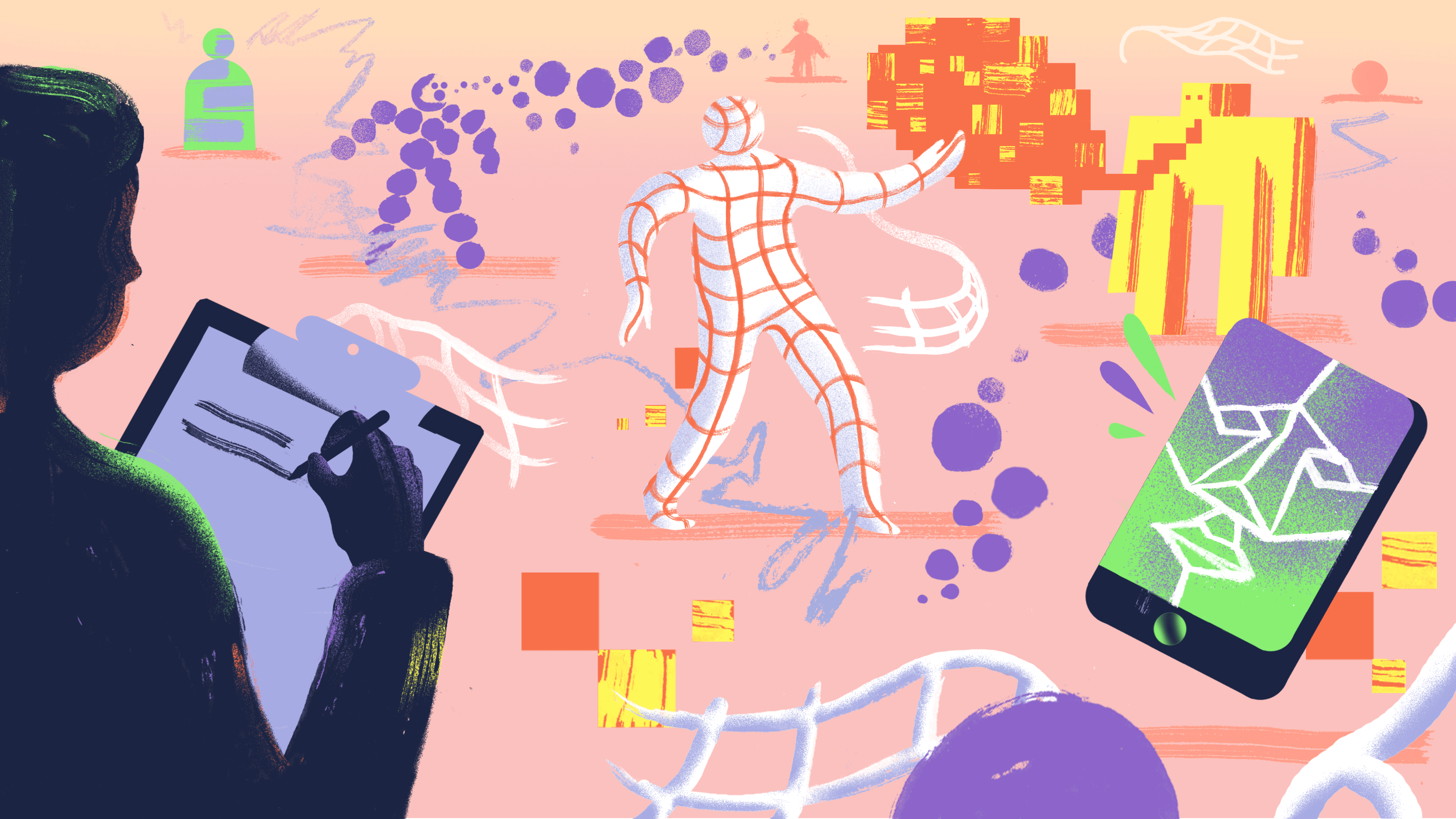AIのブラックボックス問題、MITメディアラボが新学問領域を提唱
人工知能(AI)の下した判断の理由を説明できない「ブラックボックス化」が問題視されている。だが、MITメディアラボの研究者らは、これまで生き物に対して適用してきた行動主義の手法をAIシステムに適用し、学際的な研究を進めれば、AIに説明能力を持たせる必要はないという。 by Karen Hao2019.05.03
人工知能(AI)システムのブラックボックス的な性質は、これまで盛んに論じられてきた。人々はしばしば、AIがなぜそんな決断をしたのか分からず、不快な思いをさせられているというのだ。数々のアルゴリズムが、人間の社会的、文化的、経済的、政治的なあらゆる人間の活動の仲立ちをするようになるにつれ、コンピュータ科学者はAIの振る舞いを理解する技術的方法を開発し、アルゴリズムの説明能力を求める声に応えようとしてきた。
しかし、学術界や産業界のあるグループはいま、生活へのAIの影響を理解したり制御したりするために、ブラックボックスの中身を知る必要はないと主張している。結局のところ、AIは私たちが出会った最初の不可解なブラックボックスではないというのだ。
「人々は何百年もブラックボックスを研究する科学的方法を発展させてきましたが、これらの方法はこれまで主に『生き物』に適用されてきました」と、マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボの研究者であるニック・オブラドヴィッチ博士は述べる。オブラドヴィッチ博士は、4月24日付でネイチャー誌に発表された新しい論文の共同執筆者だ。「新たなブラックボックスであるAIシステムを研究するために、同様の多くのツールを活用できます」。
産業界と学術界の多様な研究者で構成する同論文の著者グループは、「マシン・ビヘイビア(機械行動:machine behavior)」と呼ばれる新しい学問領域をつくるべきだと提案している。動物や人間をこれまで研究してきたのと同じ方法、つまり、経験的観察と実験によってAIシステムを研究しようするアプローチだ。
こ …
- 人気の記事ランキング
-
- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験
- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ
- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心
- A new CRISPR startup is betting regulators will ease up on gene-editing 期待外れのCRISPR治療、包括的承認で普及目指す新興企業
- How AGI became the most consequential conspiracy theory of our time 変人の妄想から始まった 「AGI(汎用人工知能)」 陰謀論との驚くべき共通点