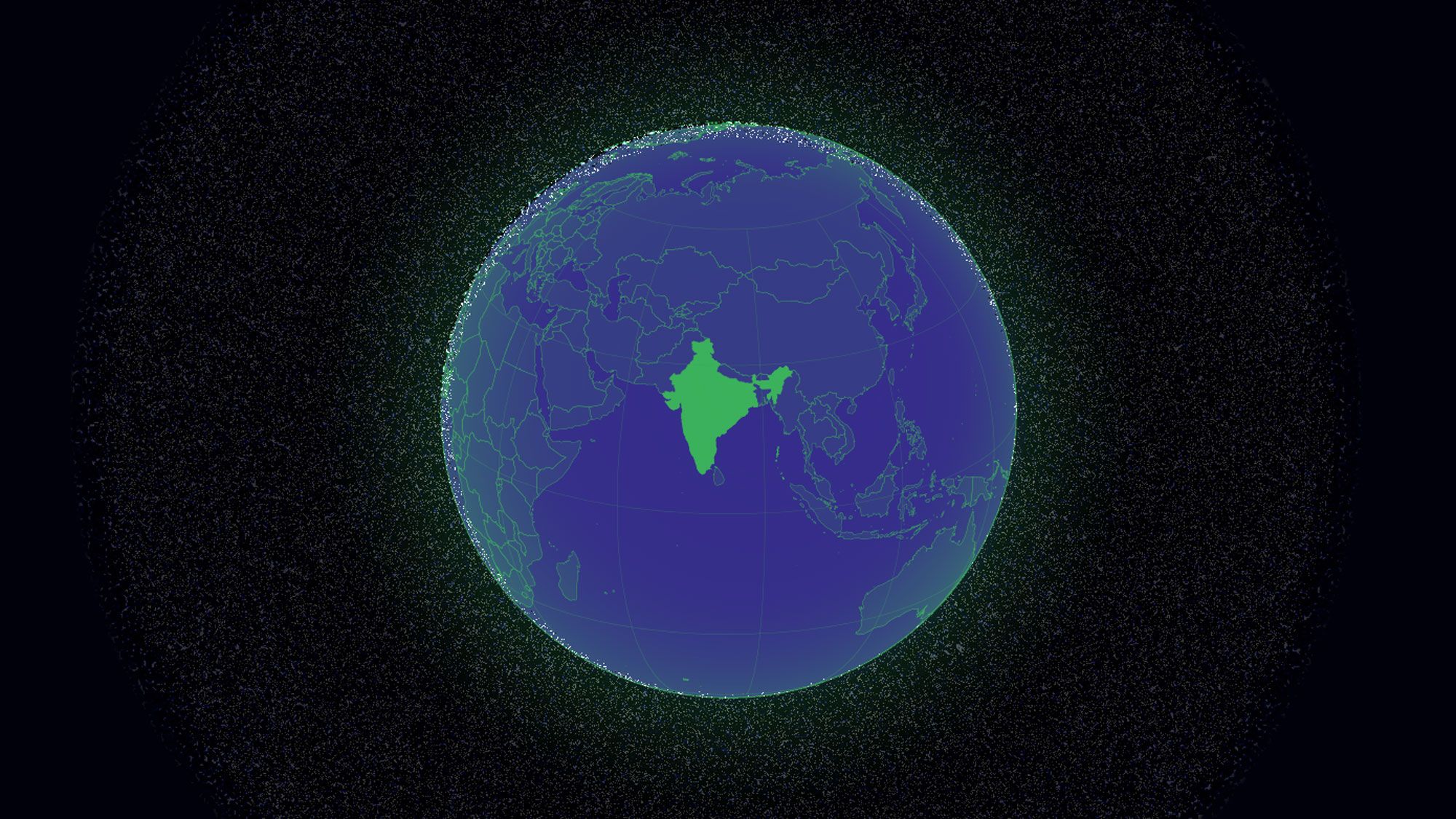巨大衛星群の打ち上げで
宇宙は早くも大混雑
衝突リスクは回避できるか?
先頃のインドによる衛星破壊実験で宇宙ゴミ(デブリ)が増えたことに米航空宇宙局(NASA)の長官は不快感を表明した。しかし今後、衛星の巨大コンステレーションが打ち上げられると地球低軌道の混雑度はますます増し、衝突したり、衝突を避けるための操作がミッションに支障をきたしたりするようになるだろう。 by Mark Harris2019.04.04
3月27日、インドはミサイルで自国の衛星の一つを撃墜したと発表した。だが、米国航空宇宙局(NASA)のジム・ブライデンスタイン長官は感心しなかった。「故意に残骸をまき散らすのは誤った行為です。宇宙を破壊すると、元に戻せなくなります」。
ブライデンスタイン長官は、ますます深刻な問題となっている宇宙ゴミ(デブリ)について言及していたのだ。稼働していない衛星、放置されたロケット、以前の衝突による残骸などが、運用中の衛星や有人の宇宙船、そして国際宇宙ステーション(ISS)にさえ脅威を与えている。
インドの衛星破壊実験で発生したデブリについてはまだ十分なデータが得られていないが、追跡会社が該当エリアをしっかり監視するだろう。ある政府高官がロイター通信に語ったところによると、ペンタゴン(米国防総省)は現時点で250の破片を監視しているという。おそらく撃破により大量の金属の破片がまき散らされただろうが、これは比較的低い高度で起こった。大部分は数カ月以内に地球の大気圏内に落ちてくるだろう。
ブライデンスタイン長官はインドのテストに不快感を表したが、デブリの専門家は現在、もっと深刻な懸念を抱いている。現在提案されている、もっと高い軌道を回る衛星の「巨大コンステレーション」は、はるかに大きな、長期にわたって継続する問題を起こす可能性がある。
今日のデブリの約半分は、2つの出来事から発生している。2007年の中国政府による衛星破壊テストと、2009年の2つの衛星(通信衛星イリジウムとロシア軍事衛星)による衝突事故だ。
しかし、地球低軌道(low Earth orbit:LEO) をはるか混雑させる計画がある。たとえば、衛星通信のスタートアップ企業であるワンウェブ(OneWeb)は、900基の小型衛星を軌道に乗せ、ブロードバンド・インターネット接続が使えない場所に衛星回線を提供する計画だ。一方、スペースXは …
- 人気の記事ランキング
-
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- A Google Gemini model now has a “dial” to adjust how much it reasons 推論モデルは「考えすぎ」、グーグルがGeminiに調整機能
- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路