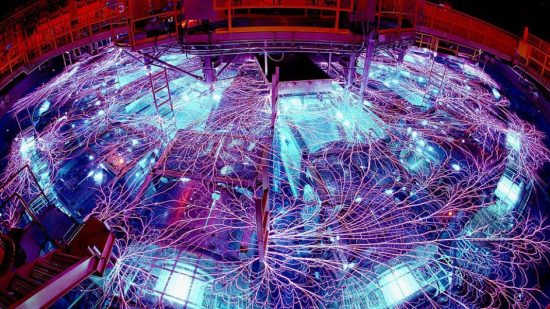世界のハブへと進化する
東洋のシリコンバレー
深センの未来
コピー製品であふれかえっていた深センは、世界に製造エコシステムを輸出するハードウェア・ハブになった。しかし、その将来は国際的な規範の順守、中国政府の圧力、労働賃金の増加などがあり、決して平坦な道のりではない。 by An Xiao Mina and Jan Chipchase2019.03.14
毎日午後4時ごろになると、深センの不規則に広がったハードウェア商店街、華強北(ファンチャンベイ)地区には梱包テープを貼るときの「キー、キー」という音が響き渡る。商店主たちが、その日に売れたもの——自撮り棒やハンドスピナー、それに電動キックボード、ドローンなどを5つずつも——を梱包しているのだ。大勢の人が「深セン・スード(Shenzhen sudu)」あるいは「深セン・スピード」と呼ばれるすばやい動きで段ボール箱をオートバイやトラックに載せたり、注文が軽い商品なら、きびきび動く電動バランス・ボードに乗ったまま車に積み込んだりしている。華強北を出た段ボール箱はグローバルな物流会社の倉庫に運び込まれ、飛行機や貨物船に載せられる。上海、シンガポールに次いで世界3番目に混雑している深セン・蛇口港(ジャコウガン)から、月間2400万トンになるコンテナ貨物の一部となって運び出されるのだ。
荷物は数日から数週間で、近くはマニラやプノンペン、遠くははるばるドバイやブエノスアイレス、ラゴス(ナイジェリア)、ベルリンといった目的地に到着する。届け先は世界最大級の都市だったり、とても小さな村だったり、さまざまだ。自撮り棒がインドの寺院の前で使われたり、ブランド名を付け替えたシャオミ(小米科技、Xiaomi)製の電動キックボードがサンフランシスコのマーケット・ストリートを走ったり、DJI(Da-Jiang Innovations Science and Technology )のドローンが世界中のあらゆる場所で飛ばされたりする。手持ちのガジェットに「メイド・イン・チャイナ」と書かれていたら、おそらく深センから来たものだろう。
深センは1970年代初頭は人口3万人の町だったが、いまや人口1000万人を超え、光り輝く高層ビルが立ち並ぶ、近代的な交通システムが整う街となった。深セン市は、特許の申請や、起業家向けのメイカー・スペースに補助金を出している。高級住宅地化と家賃上昇のせいで深センは中国でもっとも金のかかる都市となり、深セン・ブームの原動力となった工場は徐々に深センから、珠江デルタ(中国珠江河口の広州市、東莞市、深セン市、香港、マカオを結ぶ三角地帯)の他の地域へと移っていった。
深センは他の面でも変化を遂げている。ホバーボード(車輪の付いたミニ・セグウェイのようなもの)などのハードウェアだけではなく、予約や乗り捨てができる電動キックボード、アプリ制御可能なドローンといったソフトウェアを組み込んだ精巧なハードウェア、さらには翻訳デバイスや玩具ロボット、半自律型移動手段などの人工知能(AI)を搭載した製品も続々と製造されている。他者のアイデアを盗んで安価なインチキ商品を開発しているという悪評を乗り超え、深センは世界中のイノベーション、製造、知識をつなぎ合わせるハブのような存在になった。
これは深センが、途方もない資金と人材が集中しながらもシリコンバレーがなれなかったもの、つまりテクノロジー・ハブでありつつ世界のどのような国、どのような予算にも対応した製品を出荷できる都市になれたということだ。問題は、次に挙げる3つの脅威が組み合わさっている状況でも、適応と成長を続けられるかどうかにある。それは、国際化への障壁が急速に増大していること、中国政府がますます独裁化していること、そして深セン自体の成功に巨額な費用が必要になっていること——である。
模造品と技術の山賊
世界中の消費者の多くにとって深センとの最初の出会いは、「自撮り棒」のような単純な製品だった。見たところ取るに足らないもので、製造は比較的簡単なこのような製品は、「山寨(シャンジャイ:模倣品の意)」と呼ばれる製品開発・流通プロセスから生まれたものだ。字義的には「山賊」の意味を持つシャンジャイの起源は、一説によれば香港北部の丘の上にある工場群だそうだ。
オープン・ソース・ソフトウェアのおかげで、世界のソフトウェア開発者コミュニティはお互いの作業成果をコピーしてリミックスし、さまざまな異なるニーズに応えるソフトウェアをすばやく作れるようになった。これとほとんど同じ理屈でシャンジャイ方式は「ハードウェア・ミーム」、つまり調達が簡単で、容易に交換できる部品を使って設計、製造できるガジェットを供給してきた。オンライン・ニュースサイトが多数の見出しやツイートをテストしてどれが最多クリック数を得られるかを確認するように、シャンジャイ・メーカーはオリジナルとコピーを10種類リリースし、そのうちの売れ行きの良い製品を作っていく。
西側の企業なら発売までに1年から1年半かかる製品が、シャンジャイのエコシステムではたった1カ月から1カ月半でできてしまう。西側の企業がガジェットの新製品の発売予定を発表したら、発売前にすでにその製品のシャンジャイ版が棚に並んでいた、というのはよくあることだ。初期のシャンジャイ成功物語の多くは、ノキアやサムスン、アップルなど、人気の携帯電話のコピー製品だった。
これらの製品をただの安い模倣品だと片づけてしまうのは簡単だが、そこでは新しい機能を付けるために多くの実験がされていた。たとえば、デュアルSIMカードだ。アップルのスマートフォンにはつい最近搭載された機能だが、シャンジャイ製品には10年以上前から付いていた。
こうした実験ができたのは、珠江デルタの部品納入業者や小工場の活気溢れるネットワークが存在し、中国の知的所有権に対する管理が甘かったからだ。起業家は華強北の規則なく広がる巨大市場を訪れることで、何を製造すべきかを決められる。そこには数百軒もの工場が通路沿いに小さな店(多くは幅が2メートル余)を出して、それぞれの製品を展示販売している。華強北で成功した製品を競合他社が見つけてコピーするもよくあることで、中国ブランドも西側ブランドとまったく同じようにコピーされる。10製品作ってそのうちの1つが1万個程度ヒットしてくれれば十分な利益が出て、他の9製品の赤字をカバーできたのだ。
ただし、次のハンド・スピナー(ボールベアリングを内蔵した玩具)は常に見つかるのだろうが、シャンジャイにもシャンジャイなりの限界はある。海外に足掛かりを得ている企業は、相手国の知財法に適合せざるを得ない。ハンド・スピナーやホバーボードなどの製造を卒業し、インターネット接続式電球やAIデバイスを製造し始めるにつれて、デザインやブランディングのノウハウも必要になってくる。
もしシャンジャイが発展できないままだったら、それはグローバル化の歴史における興味深い逸話程度に留まっていただろう。だが、深センはまだ、止まるところを知らない。
工場の生産ラインからデザイン・スタジオまで
デザイン・コンサルティング会社であるイノゼン(Innozen)のオフィスは、華強北の喧騒地帯からタクシーに乗って少し行ったところにある。 落ち着いたオープンスペースのオフィスを抜け、案内されたのは必要最低限に装飾された白い会議室だ。部屋には賞状や盾を飾った棚があり、国際的なデザイン賞の受賞を示すものもいくつかあった。
イノゼンのマイケル・ジェン共同設立者は、「シャンジャイ製品は一種の『目くらまし設計』なのです」と説明してくれた。彼によると、シャンジャイの設計プロセスには統一的な戦略はまったくないが、「技術的な障壁は下がり続けている」そうだ。
新種のコンサルティング企業であるジェン共同設立者の会社は、現地では工業デザイン会社と呼ばれている。深センにはこうした会社が続々と誕生しており、シャンジャイ製品よりも精巧なもの(たとえば通訳イヤフォンや …
- 人気の記事ランキング
-
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製
- Meet the researchers testing the “Armageddon” approach to asteroid defense 惑星防衛の最終戦略 科学者たちが探る 「核爆発」研究の舞台裏