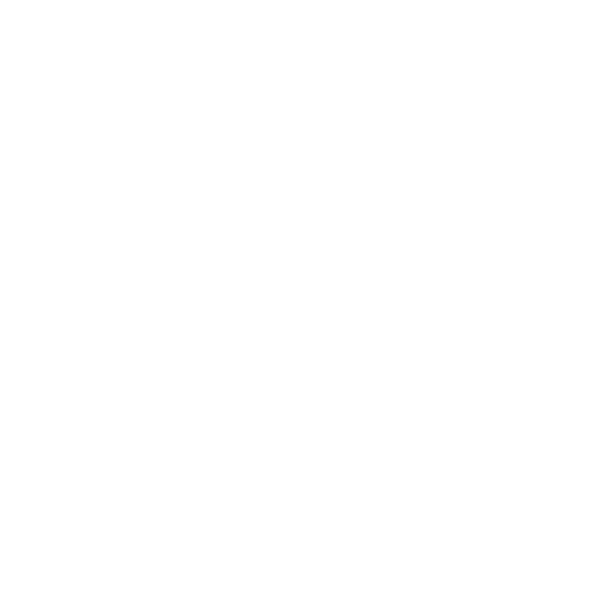日本の食品酒類総合企業、サントリーグループの研究者である久津見ゆうか(Yuka Kutsumi)は、スマートフォンの内蔵マイクで集音した腸のぜん動音(腸音)を認識する深層学習モデルを構築した。2023年2月にはこのモデルを応用したスマートフォンアプリ「腸note(GutNote)」がリリースされている。
腸音は腸の状態を示す指標の1つとされ、通常は経験を積んだ医師が聴診器で聴き取って所見を得ている。そのことに着目し、腸noteはスマホだけで腸音を測定・解析し、腸の健康状態をより良く改善することを目指したアプリであり、個人が健康行動を始めるハードルを下げ、継続性を高めることにつながる。
久津見は、米国カラマズー大学で生物学を専攻した後、グランドバレー州立大学大学院コンピューター・情報システム学部とコーネル大学大学院生命科学でそれぞれ修士課程を修めた。その後2017年7月にサントリーへ入社し、生化学・遺伝情報学に精通した研究者としての知見と、深層学習を扱うデータサイエンティストとしての経験を生かしてこの技術を開発した。
アプリの開発に当たっては、約70時間の腸音データに対してスクリーニングとアノテーション(ラベル付け)を実施し、腸音認識モデルを開発。100名規模の臨床試験を実施している。腸noteは、腸音だけでなくユーザー自身が日々、便通や睡眠、体温などの体調データを入力することにより、パーソナライズされた食習慣や運動習慣の改善を提案する。
久津見の取り組みは、これまで取得が難しかった「音」という生体信号をスマートフォンという多くの人が所有するデバイスで取得できるようにしたものだ。加えて、腸音データを長期にわたって収集することでデータから新たな研究シーズが生まれ、ユーザーにさらなる価値を提供するエコシステムを構築できる可能性もある。
久津見は現在、英国ロンドンにあるサントリーの研究所で別のプロジェクトに取り組んでいる。「デジタルヘルスのグローバルな課題にも着目しながら、研究活動に邁進していきます」と言う久津見は、新たな視点・環境を得て活動のフィールドを広げていく。
(畑邊康浩)
更新履歴:アプリについての説明を明確にするため、一部内容を更新しました。(2023年11月14日)
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製