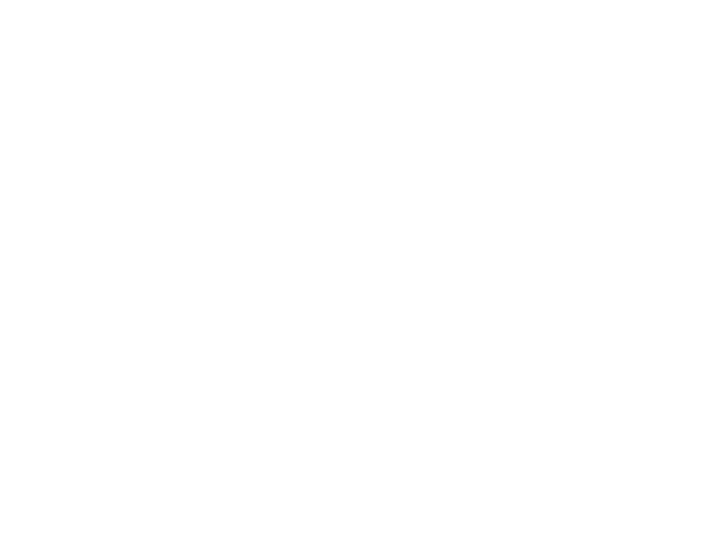がんは早期に発見して治療できれば生存率が上がるとされている。例えば、卵巣がんの5年相対生存率は、遠隔転移にまで至るほど発見が遅れると23.9%だが、ステージの早い限局のときに発見できると92.5%と非常に高い(国立がん研究センター「がん種別統計情報」による)。
小野瀨隆一(Ryuichi Onose)がCEOを務めるクライフ(Craif)は、同社のビジジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を目指し、がんの進行の指標となるバイオマーカーを、尿を用いて検出、解析する。尿は、簡単で非侵襲的(体を傷つけない)、高精度に検査できるという条件を兼ね備えている。クライフが開発した尿検査はがん種の分類にも成功している。小野瀨は、「がん種が分かってはじめて追加検査を実施できるため、この点にこだわって研究開発を進めてきた」と話す。
小野瀨は大学卒業後に商社に入社し、サイドビジネスを始めたことをきっかけにスタートアップに関心を持つようになったという。起業するときに考えたのが「人類の進歩に貢献したい」ということだった。社会に大きなインパクトを与えるのはがんであり、祖父母をがんで亡くしたことも事業展開の後押しとなった。
小野瀨自身は医療やバイオ研究の経験はないが、がん早期発見検査の精度の低さを知り、事業に賛同する専門家を採用して技術を高めていった。ナノバイオマーカーを効果的に捕捉、計測、分析、データベース化する「NANO IP(NANO Intelligence Platform)」を構築し、がんに関わる細胞間のクロストークを高精度に読み取るがん検査を開発。成果は国際学会でも発表され、2022年2月に全国の医療機関で『マイシグナル(miSignal)』シリーズとして提供を開始。現在では一度に最大で7つのがん種(大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、すい臓がん、食道がん、卵巣がん)をがん種別にリスク判定できる検査に進化し、2022年11月には自宅完結型検査の販売もスタートした。
クライフが分析する主な分子は、miRNA(マイクロRNA)というもので多くの種類があり、がんに限らずさまざまな疾患と関連するものがある。製薬企業などに向けてR&Dサービスも提供しており、クライフは数々の疾患の早期発見に貢献するプラットフォーマーになる可能性も秘めている。
(島田祥輔)
- 人気の記事ランキング
-
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製