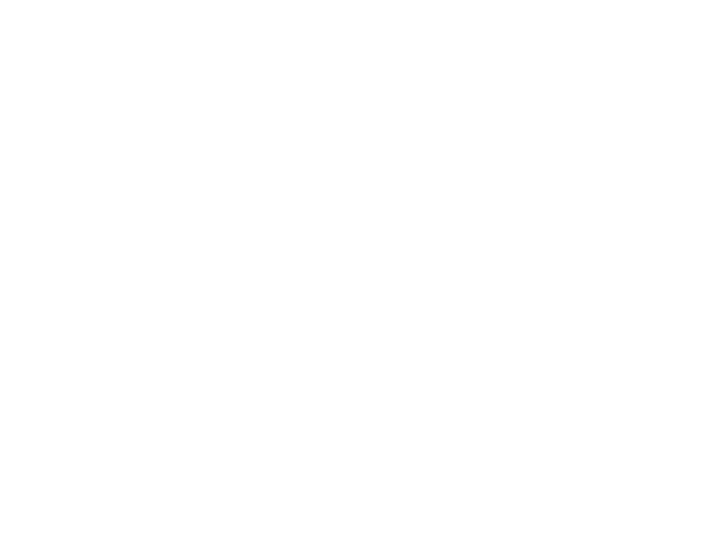日本の高度経済成長期には、高速道路や橋、トンネルやダムなどの公共インフラが集中的に整備された。現在、それらのコンクリート構造物は老朽化が進み、およそ半分が今後10年以内に耐用年数を迎えるとされている。
一方、建設業界は3K(きつい、汚い、危険)のイメージから若年層の入職が少なく、高齢化が急速に進んでいる。とりわけ社会インフラの維持管理・更新を担うコンクリートの型枠職人は55歳以上が4割を占め、10年以内に3分の1が減少するとの見方もある。人手不足は喫緊の課題だ。
この課題に挑むのが、岩本卓也(Takuya Iwamoto)がCEOを務める2019年6月創業のスタートアップ企業、ポリウス(Polyuse)だ。コンクリートを積層して構造物を造形する建設用3Dプリンター技術を開発し、製品とその運用をサービスとして提供している。従来の型枠を用いた工法に比べて複雑な形や手間のかかる形を3Dプリンターで造形することにより、施工期間の短縮や省人化を実現する。
建設用3Dプリンター技術は、一般的な3Dプリンターで用いるレジンではなく、不均一な粉末体であるセメント材料を用いて水和反応によって硬化させて造形する。温度など環境変化の影響を受けやすく、特に建設現場などの野外では状態変化の制御が難しい。これらを制御するには材料、機械、システムの3分野を適切に調整する必要がある。
特筆すべきは、創業から3年足らずで日本の厳格な建築基準や公共工事の安全基準をクリアする水準まで技術の品質を引き上げた開発スピードだ。全国各地の中堅・大手建設会社との対話を重視し、現場のニーズや課題を捉えながら実証を重ね、早期実用化につなげた。2022年4月には、国内で初めて公共工事での3Dプリンター施工を実施。全国の自治体や鉄道会社、道路会社などの工事でも今後活用される予定だ。
「各関係者と一緒になって20年後の未来のインフラを持続可能な形で施工し、人の暮らしを安定的に支え続けられるチャレンジをしていきたい」と話す岩本への建設業界の期待は大きい。
(畑邊康浩)
- 人気の記事ランキング
-
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- This Texas chemical plant could get its own nuclear reactors 化学工場に小型原子炉、ダウ・ケミカルらが初の敷地内設置を申請
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製