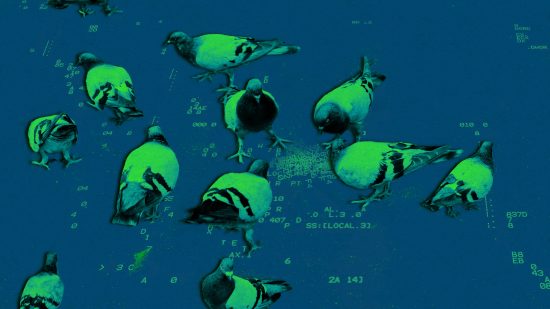 Cover Story
Cover Story
マシン・プログラミングで 人海戦術に終止符、 AIコーディングに第二の波
生成AIがいま、ソフトウェア開発を変えようとしている。コードの自動補完から始まった支援は、プログラミングの本質を理解し、人間に代わってコードを考案するレベルへと進化しつつある。第一世代ツールが開発現場に浸透する中、AIコーディングは「第二の波」を迎え、数百人規模の開発チームを必要とした時代に終止符を打とうとしている。
by Will Douglas Heaven-
スターゲートは過剰投資か? ディプシーク・ショックで広がる波紋
中国のスタートアップ企業ディープシークが発表した大規模言語モデル「DeepSeek-R1」が、米国のAI業界に衝撃を与えた。ソフトバンクらが主導する5000億ドル規模のAIデータセンター投資計画の必要性が、改めて問われている。
by James O'Donnell -
水素は「掘る」時代に? 地下水素は地球を救うか
化石燃料に代わるエネルギー源として水素に期待する声は大きい。しかし、水素を生成するコストを考えると経済的な選択とは言えない。ところが、近年の研究で地中に膨大な量の水素が埋蔵されていることが分かった。しかも、化石燃料採掘で培った技術やノウハウを利用して採掘できるという。
by Casey Crownhart -
「2匹の父」を持つマウスが誕生、中国チームがCRISPRで
中国の研究チームは遺伝子編集技術「CRISPR」を用いて、2匹の雄マウスのDNAを持つ「二父性」マウスを作り出す方法を発見した。この方法で誕生したマウスの一部は成体になるまで生きたが、ヒトへの応用は今のところ不可能だ。
by Jessica Hamzelou -
eムック「2025年に注目すべき気候テック企業15社」特集号
MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.69 / 2025.01をリリースした。特集は「2025年に注目すべき気候テック企業15社」。
by MIT Technology Review Japan -
「感染症と遺伝の関係を解明、次のパンデミックに備え」金井仁弘
MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、マサチューセッツ総合病院所属の金井仁弘氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。
by MIT Technology Review Japan -
資金流入で競争加速、
2025年のロボット開発は
どう動く?人型ロボットの実用化テストが本格化し、AIを活用した新たな学習手法も登場。2025年は実験室から現場へと活躍の場を広げるロボットの価値が問われそうだ。
by James O'Donnell -
地球を化学工場に——地下資源でアンモニアを作る新スタートアップ
肥料の原料として知られるアンモニアは生活に欠かせない化学物質だが、その製造工程で大量のエネルギーを消費し、相当な量の二酸化炭素を排出してしまう。MITの研究者らが立ち上げたスタートアップは、地下の環境を利用した製造の実用化を目指す。
by Casey Crownhart -
「電子ナノ絆創膏で医療とスポーツに革新を」 山岸健人
MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、東京大学所属の山岸健人氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。
by MIT Technology Review Japan -
体外受精で残った「余剰胚」をどう扱うべきか?
IVF(体外受精)が上手くいって、妊娠したときに、胚が余ることがある。この余った胚(余剰胚)をどうするか、IVF利用者の間でも選択が分かれる。決断を先送りにしたままの利用者も少なくない。
by Jessica Hamzelou -
米制裁で磨かれた中国AI「DeepSeek-R1」、逆説の革新
オープンAIの「o1」に匹敵する性能を持ちながら、運用コストは数分の一。米国による半導体輸出規制下で誕生した中国発の言語モデル「R1」に、AI業界が沸いている。制約を逆手に取った効率重視の開発が注目され、オープンソース戦略と相まって、規制が新たなイノベーションを促す皮肉な展開となっている。
by Caiwei Chen
