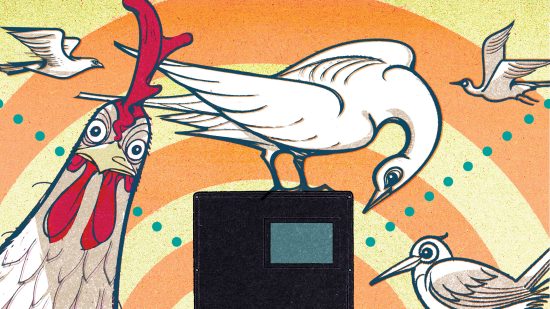分子レベルの急激な老化は40代と60代にやってくる
スタンフォード大学の研究チームが25歳から75歳までの108人から収集した生物学的データを分析したところ、従来の緩やかな老化の概念を覆す発見があった。分子レベルで急激に老化が進むポイントが40代と60代の2度あることが明らかになったという。 by Jessica Hamzelou2024.08.27
- この記事の3つのポイント
-
- スタンフォード大学の研究チームが40代と60代に老化の波があることを発見した
- 40代の変化は原因不明だが60代の変化は心血管疾患などと関連している
- ただし、老化の進行は直線的ではなく個人差が大きいため一概には言えない
この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。
人間の老化にはいくつかの波があるようだ。最近、私はその可能性を示す研究について知った。老いにはゆっくりと徐々に衰えていくようなイメージがあるが、この研究に携わった科学者チームによると、分子レベルでは急激に老化が進むポイントが2度ある可能性が高いという。一度目の変化は40代で起こるそうだ。
スタンフォード大学のマイケル・スナイダー博士らの研究チームは、この研究のためにカリフォルニア州在住の25歳から75歳までの108人のボランティアから膨大な生物学的データを収集した。できるだけ多くの情報を集めてから年齢に関連するパターンを探すアプローチである。
このアプローチによって驚きの事実が明らかになるかもしれない。40代という年齢の影響はそのひとつだ(ちなみに、40代が一般的に「中年」であることを知って愕然としている)。老化に関する大きな疑問の解明につながるかもしれないし、老化の過程で起こる不快に対抗する医薬品の発明のきっかけになる可能性すらある。
だが、そう簡単な話ではない。そして、中年になったからといって幸福感が急落するとは限らない。理由を説明しよう。
まず、8月14日に「ネイチャー・エイジング(Nature Aging)」に掲載された当の研究である。スナイダー博士らのチームは、ボランティアから、遺伝子発現、タンパク質、代謝物、その他さまざまな化学マーカーをはじめとする膨大なデータを収集した。また、ボランティアの皮膚、便、口腔、鼻腔からサンプルを採取し、常在している可能性のある微生物群について調査した。
各ボランティアは平均1.7年の期間、数カ月ごとにサンプルを提供した。最終的にチームが集めた合計5405点のサンプルには、13万5000種を超える生物学的特性が含まれていた。「念頭にあったのは、人々の健康状態の全体像を完璧に把握することです」とスナイダー博士は説明する。
同博士らがデータを分析したところ、測定した分子や微生物の約7%は、時間の経過とともに直線的にだんだんと変化していくことがわかった。その一方、81%は特定のライフステージで変わっていた。特に重要な段階は2回ある思われる。44歳前後と60歳前後だ。
60歳で起こる顕著な変化は、腎臓や心臓の機能、動脈が狭くなるアテローム性動脈硬化症などの疾患に関連しているようだ。心血管疾患を発症するリスクが加齢とともに劇的に高まることを考えればうなずける。実際、40歳から59歳の約40%が心血管疾患にかかり、60歳から79歳ではこの数字は75%に上昇するのだ。
だが、40歳前後で起こる変化にスナイダー博士は驚愕した。それは考えてみれば直感的にわかることだと言う。多くの人は、40歳を超えると身体に衰えを覚え始める。たとえばケガが治りにくくなったことに気づいたりする。
その他の変化は、脂質やアルコールの代謝機能が40代に入ると激変することを示しているが、その理由はいくつかの点から説明しがたい。
まず、たとえばアルコール代謝の変化については、アルコールを分解する機能の低下ゆえか、年をとるにつれてアルコールの摂取量が減るだけのことなのか、はっきりしない。
結局、老化の謎の核心に行きつく。人間が衰えていくのは内蔵されたプログラムが原因か、それとも単に生活の結果なのか。
答えはまだわかっていない。おそらく両方が合わさって起こることなのだろう。人間の身体は年月がたつ間にさまざまな環境ストレスにさらされる。さらに、細胞が老化するにつれて、細胞の分裂能力が低下し、時間がたつにつれて蓄積した分子のゴミを除去する機能も衰えていく。
また、この研究では、筋力や虚弱といった老化の生理学的指標を測っていないため、状況を判断するのは難しい、とスコットランドのグラスゴー大学の老化生物学者、コリン・セルマン教授は指摘する。
あまり科学的ではないかもしれないが、別の疑問も浮かぶ。このような分子の変化は憂慮すべきものなのか。私はもうすぐ40歳になる。大騒ぎしたほうがいいのか。スウェーデン、ストックホルムのカロリンスカ研究所で老化の分子疫学を研究しているサラ・ヘッグ准教授に尋ねてみた。ヘッグ准教授は「いいえ」と即答した。
スナイダー博士のチームは膨大なデータを収集したが、それは比較的短い期間に比較的少数の人々が提供したものである。人体に分子の変化の2回の波が起こるのを観察するには20年から30年が必要だが、それだけの長期間の追跡調査を受けた被験者はいない。
「これは観察研究であって、別の人同士を比較するものです」とヘッグ准教授は説明してくれた。「自分にも同じことが起こるというエビデンスは一切ありません」。いずれにせよ、20年、30年も時が流れれば、人生にはさまざまなことが起こるものだ。スポーツを始める人もいるだろう。禁煙する人、肉を食べるのをやめる人がいてもおかしくない。
とはいえ、今回の研究結果は、老化は直線的なプロセスではないという説を裏付けている。
「40歳あたりから人生は下り坂だという嘆きは今に始まったことではありません」とセルマン教授は言う。「でも、それほど単純な話ではないのです」。
スナイダー博士は、このような研究をきっかけに、老化に伴って起こる有害な分子変化に対抗する上で何が治療の対象になり得るのかが明らかになっていくのを期待している。「人間の健康寿命は寿命より11年から15年短いのが現状です」とスナイダー博士は言う。「誰にとっても、死ぬまでなるべく長く健康に生活できるのが理想でしょう」。
その理想をかなえる医薬品はまだ存在しない。今のところは結局、よく食べ、よく眠り、適度に運動し、喫煙やアルコールなどの絶対にダメなものを避けるといういつものアドバイスになってしまう。
セルマン教授と話したのはたまたまひどく疲れた日だったので、私は日暮れにワイングラスを傾けるのが楽しみだと言ってしまった。アルコール摂取に「安全なレベル」は存在しないことが研究でわかっているにもかかわらずである。
「ちょっぴりのアルコールは実に美味しいものですよね」とセルマン教授も同意した。そして、老化をテーマにしたカンファレンスで目にしたことを話してくれた。出席者の中に、カロリー制限を実践している団体のメンバーがいた。摂取カロリーを減らすと寿命がグッと延びるというのである(人間にも効果があるかどうかはまだわかっていない)。「豪華な食事が出たのですが、その人たちはめいめい小さなはかりを持っていて、サラダをのせて重さを量っていました。私には、それはみじめな生き方としか思えませんでした」。
私はとにかく、健康的な生活習慣と自分が楽しいと思える生活習慣をバランスよく選択したい。そして、何をやめても、人間の寿命は劇的には延びないということは覚えておいたほうがいいだろう。セルマン教授が「特別なことを実践するのはいいですが、結局、寿命が尽きたらそこまでです」と言うとおりである。
MITテクノロジーレビューの関連記事
老化を狙い打つ薬はまだない。それでも、長寿クリニックは次々と現れ、健康寿命を延ばすというさまざまなサービスを超富裕層向けに提供している。現在目指しているのは、長寿医学の制度化だ。
超富裕層といえば、アンチエイジング(抗老化)治療の探求のためなら何百万ドルでもつぎ込む長寿マニアのイベントにも行ってみた。やや妙ではあったが、とても興味深い体験だった。
昨今、若返りの効果が期待されている計画はたくさんある。しかし、最も多くの注目と資金を集めているのは、細胞のリプログラミングだ。MITテクノロジーレビューのアントニオ・レガラード編集者が、この分野の将来性を検討する記事を書いている。
科学者たちは、人の年齢を今までとは違う方法で測れないか考えている。誕生日を迎えた回数だけではなく、老化の進み具合や死期の近さも考慮しようというのだ。私は実際にその種の生物学的老化検査を受けてみた。決して喜べる結果ではなかった。
医学・生物工学関連の注目ニュース
- エムポックス(サル痘)の感染がコンゴ民主共和国とその近隣諸国で急増し、世界保健機関(WHO)は、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言した。 WHOのテドロス・アダノム・ゲブレイェスス事務局長は、Xに投稿した報告の中で「コンゴ民主共和国東部で新系統(サブグループ)のエムポックスが検出され、急速に拡大していること、過去にエムポックスの発生が報告されていなかった近隣諸国で検出されていること、アフリカ内外で感染がさらに拡大する可能性があることは非常に憂慮される」と述べた。「このアウトブレイクを食い止め、人命を守るには、国際的に協調した対応が不可欠だ」。(WHO)
- 義肢には企業のロゴが付いていることが多い。ユーザーにとっては、不本意なタトゥーかもしれない。(アトランティック)
- インドの試験施設が、400種以上の医薬品に関連する不正データを米国食品医薬品局(FDA)に提出した。しかし、これらの医薬品は米国市場から回収されていない。主に医薬品の副作用の調査をしている非営利団体の創設者兼代表は、今の状況を改善しなければならないと語る。(スタット誌)
- 抗生物質は腸内マイクロバイオームに影響を及ぼし得る。だが、帝王切開を受けた人に投与される抗生物質は、赤ちゃんのマイクロバイオームにほとんど影響しない。授乳のしかたのほうが、はるかに大きな影響があるようだ。(セルホスト & マイクローブ)
- 人が予期せぬ感染症にかかったとき、必要なのは医師だけではない。獣医の「病気探偵」は、動物から人間へ、あるいは人間から動物への感染の広がり方を追跡するうえでなくてはならない存在だ。(ニューヨーカー)
- 人気の記事ランキング
-
- Anthropic can now track the bizarre inner workings of a large language model 大規模言語モデルは内部で 何をやっているのか? 覗いて分かった奇妙な回路
- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #32 Plus 中国AIをテーマに、MITTR「生成AI革命4」開催のご案内
- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声
- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法
- Tariffs are bad news for batteries トランプ関税で米電池産業に大打撃、主要部品の大半は中国製
- ジェシカ・ヘンゼロー [Jessica Hamzelou]米国版 生物医学担当上級記者
- 生物医学と生物工学を担当する上級記者。MITテクノロジーレビュー入社以前は、ニューサイエンティスト(New Scientist)誌で健康・医療科学担当記者を務めた。