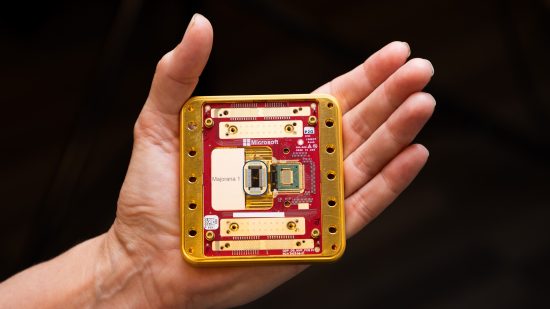なぜ搾取は起きるのか?東大研究者が「囚人のジレンマ」で解明
一見すると対等な状況でも、搾取的な関係を構築できる。東京大学の研究者による新たな「囚人のジレンマ」の研究によって、搾取の構造が明らかになった。 by Emerging Technology from the arXiv2019.06.06
ゲーム理論における代表的な理論の1つに、「囚人のジレンマ」がある。この思考実験では、犯罪を犯して逮捕された2人のプレイヤー(ここではアリスとボブとしよう)が、互いに話し合えないように隔離され、相手を裏切るような司法取引を持ちかけられる。
しかし、裏切りの報酬システムは複雑だ。1人のプレイヤーが自白し、もう1人のプレイヤーが自白しなかった場合、自白したプレイヤーは釈放され、自白しなかったプレイヤーには6カ月の刑が科せられる。両方のプレイヤーが自白すれば、両方とも3カ月の刑を受ける。しかし両方のプレイヤーが協力して黙っていれば、両方とも1カ月だけの刑で済む。
プレイヤーにとって最良の戦略はどれだろうか。黙って協力し合うべきか、あるいは裏切って自白するべきか。
経済学者、進化生物学者、ゲーム理論家が、長い間さまざまな戦略を詳細に研究してきた。1回限りのゲームであれば、自白したプレイヤーに最長の刑が科せられないことが保証されているので、裏切って自白するのが最良の戦略であるのはわかっている。
しかし、ゲームが繰り返されると、プレイヤーは経験を生かして新しい戦略を練れるようになり、復讐したり、協力したりするようになる。実際、いわゆる繰り返しゲームとして実施される囚人のジレンマは、社会的生物の間で協力的行動がいかに発展したかを示している。これにより、かつて進化生物学者にとって重大であった問題が解決された。
もう1つ未解決の問題は、搾取が社会でいかに発展してきたかだ。社会的生物の間で、どのようにして個人が他者を利用して自分の利益を増やすようになったのだろうか。
明白な答えの1つは、力のある人はその力を使って力の弱い人を利用できるということだ。この答えは同時に、力が拮抗する個人間では搾取的行動が起こりえないことを示唆する。それでもなお、広い規模で頻繁に搾取が見られる現状は、搾取は起こるべくして起こっているということを示唆している。搾取は一体どのように起こるのだろうか。
東京大学の大学院生である藤本悠雅と金子邦彦教授の研究が1つの答えを出している。この研究では、繰り返しゲームとしての囚人のジレンマを使って、1 …
- 人気の記事ランキング
-
- Why handing over total control to AI agents would be a huge mistake 「AIがやりました」 便利すぎるエージェント丸投げが危うい理由
- OpenAI has released its first research into how using ChatGPT affects people’s emotional wellbeing チャットGPTとの対話で孤独は深まる? オープンAIとMITが研究
- An ancient man’s remains were hacked apart and kept in a garage 切り刻まれた古代人、破壊的発掘から保存重視へと変わる考古学
- How to have a child in the digital age 「あなたはもうママですね」 ネット・デジタルが約束する 「完璧な出産」の幻想